連載第1回「家族による慰労会」
このたび、図らずも本欄への執筆の機会を与えられました。
未熟な若輩にとって、外に向かって語るべき何があるか、省みて心許ない限りです。しかし、ここで一度立ち止まって、今までのことを整理してみようと思いなおし、お受けすることにしました。振り返ってみると、自分一人でやれたことは何一つなかった、数多くの方々のご指導や応援を受け、書物に啓発され、たどたどしい今日の私があることを痛感しております。
まことに恥多き人生ですが、これまでに出会った優れた人、心に残る言葉を中心に綴ってみたいと思います。凡人の体験記としてお読み下されば有難いことです。
さて、私はNEXCO中日本(中日本高速道路株式会社)会長を平成22年6月に退任しました。急なことで、ご挨拶を十分にできなかったことを申し訳なく思っています。
名古屋での四年間は公私ともに充実した日々で、お世話になりました社内外の多くの皆さまに、心からお礼を申し上げます。私にとって尾張は、江戸時代以来の父祖の地です。これまでは冠婚葬祭や仕事の出張で訪ねることはあっても、住むのは今回が初めてのことでした。ここで職業人生の区切りとなる仕事に、心おきなく取り組むことができたことを感謝しています。
人生は人縁・時縁・地縁の賜物です。
私は昭和16年1月に生まれました。太平洋戦争の直前です。それからおよそ70年、数え切れないほど多くの先輩・師友に導かれて今にいたりました。誠に有り難いことです。
そうした数多いご縁のなかでも、家族の縁はとりわけ大事にしたいと思います。私が任を終えて東京に戻った時に、子供と孫が全員集合して、慰労会をやってくれました。社会人になりフルタイムの勤務を続けて47年、ようやくここで一段落したことを記念して開かれたものです。心のこもった嬉しいひと時を、二男二女とその伴侶、孫四人、私たち夫婦を入れて総勢14人で過ごしました。大連にいる次男の家族が、小五の孫の夏休みで帰国した時に集まったのです。子供たちは独立して、それぞれの道を元気に歩んでいます。同じ親から生まれながら、一人ひとり個性的であることは驚くばかりです。親のいなくなった後も、兄弟姉妹、孫も含めて仲良くやっていって欲しいというのが、妻景子とともにいつも語り合っている念願です。
以上
連載第2回「父祖の地に帰って」
平成18年6月、私はNEXCO中日本の代表取締役会長CEOに就任しました。
この会社は、日本道路公団が平成17年10月に三分割民営化されたうちの一つで、名古屋に本社をおき、1都11県の高速道路を建設・管理し、休憩施設を営業しています。さっそく私は市内に居を定め、初めての名古屋生活を開始しました。
尾張は江戸時代にさかのぼる私の父祖の地です。豊明村(現豊明市)ですが、法事で訪ねた時に子供心に覚えている風景は、畑が広がる緩やかな丘陵地帯でした。それが今では交通の便も良くなり、見違えるような住宅地となっています。発展する大都市郊外の典型を見るような気がします。
祖父敏夫(写真)は明治8年の生まれ、昭和7年に亡くなりましたので、私は会ったことがありません。祖父は日露戦争に従軍し、奉天会戦で大怪我を負い、帰国して染物会社を立ち上げました。強い事業家精神の持ち主だったのでしょう。工場は現在の名古屋市西区役所辺りにあり、一時はたいそう繁盛したようですが、昭和大恐慌のあおりで倒産したと聞かされてきました。親戚には村会議員を務めた者もおり、長年地元に根付いた存在であったようです。記録をたどりますと、名古屋市に住む私の従兄弟で11代目になります。
私の友人は、「ご先祖に君は呼ばれたんだよ」と言ってくれましたが、なるほどそうかもしれません。そんな思いもあって、着任直前の6月下旬に妻を伴って先祖のお墓参りをし、あわせて伊勢神宮にも参拝しました。実は伊勢神宮は昭和39年の秋、新婚旅行で訪れて以来のことですから、二人とも長い間ご無沙汰したものです。宇治橋を渡り森に入った時に感ずる、言葉に表せない清々しい雰囲気は昔のままで、あらためて感動しました。
この時以来、年二回の伊勢神宮参拝を欠かしたことがありません。正月は高速道路の安全祈願で会社の人たちと共に、年半ばには子供や孫と連れだって家内安全を祈っております。
平成21年11月3日には宇治橋の渡り初めにお招きを受け、恒例の三代家族に従って、妻とともに朝日に輝く香り豊かな橋を歩き、欄干を手でさすって感銘を新たにしました。風の強い寒い日でしたが、季節外れのトンボが一匹、欄干の日だまりの中で、身動きもせずにじっとしていた姿が忘れられません。
以上
連載第3回「九死に一生を得た水戸の大空襲」
昭和20年の終戦は、水戸市大町で迎えました。
お城跡のすぐ近くある、母元子の実家に兄正典と三人で東京から疎開していたのです。父典夫は満州(中国東北部)に高射砲隊の一兵卒として従軍中でした。父が抑留生活を終えて帰国するまで、母は食べざかりの男の子二人を抱え随分苦労したようです。
終戦間際の8月2日に、水戸市は連合軍の大空襲と艦砲射撃の標的となり、たちまち焼け野原になりました。それまでにも何度か庭の防空壕に逃げ込みましたが、この日は桁違いの爆撃で、母は着のみ着のまま、防空壕を飛び出し、私たち兄弟を守り、那珂川に向かって避難したそうです。
空襲が終わって戻る途中の道路には大きな穴がいくつも開き、黒焦げの人が転がり、あちこちがまだ燻っていました。わが家はただ残骸のみ、焼夷弾の金属蓋で火傷をしたほどです。私は四歳でしたがその後の10年間ほどは、炎に追いかけられる夢を見てうなされました。恐ろしい被災体験が、人生最初の強烈な記憶となったのです。
この時私は母に手を引かれながらも、一生懸命に走って避難したと思い込んでいたのですが、後年大学生の頃でしょうか、父と一杯やっている時にたしなめられ、初めて真相を知りました。「走って逃げたのはお兄ちゃんですよ。あなたは本当に重かった」と。また、「あの時あなたは、河原の桑畑でガスに巻かれて危なかったのです。土を掘って顔を押し込み、何とか呼吸ができるようになったのです」とも。母のお蔭で私は九死に一生を得たのです。得意の鼻をへし折られ、見るからにきゃしゃな母にそれ以来すっかり頭が上がらなくなりました。
焼け出された後は不自由なテント生活をし、まもなく水郡線の沿線、山方宿に親戚を頼って移り、農家の狭い納屋暮らしが始まりました。鮎で有名な久慈川が流れており、魚釣りやウナギ取り、水浴びでよく遊びました。
泳ぎを教えてくれた兄は四つ上でしたが、私が久慈川の早瀬に足を取られ流された時、渦を巻く淵に引き込まれる寸前で助けてもらった記憶があります。その兄は昭和22年、小学校五年生の時に心臓弁膜症で亡くなりました。「今なら助けられたのに」と、父母の嘆きと悲しみは生涯続きました。子供は決して親より先に逝ってはいけないのだ、自分は長生きしようと子供心に誓った覚えがあります。
以上
連載第4回「子供心に夢を灯す」
少年時代の学校の先生の言葉は、時にその子の一生に大きな影響を与えるものです。
私は昭和22年に茨城県の疎開先、水郡線の沿線にある山方宿で小学校に入り、水戸市などへの転校を繰り返し、東京に戻ったのが3年生の時、四つ目の小学校でした。3年生の時に、学芸会で浦島太郎の端役を貰いました。お蔭で今でも「昔々浦島はー、助けた亀に連れられてー」と全曲歌うことができます。
4年時から卒業まで担任となった勝村静枝先生には、勉強面でも生活面でも相当厳しく鍛えられました。姿勢の悪い子はいつも鯨尺を背中に差し込まれて直されましたし、規則を破ったり宿題を怠ければ、必ずバケツを持って立たされるか、廊下拭きの罰を与えられました。私も何回やらされたか分かりません。口癖は、「背筋まっすぐ、心まっすぐ」とか、「世のため、人のため」「刺身のツマになるな」など。晩年は静岡県の老人ホームに住み、趣味の集まりで上京しては突然電話がかかり、「矢野君お元気?東京に来ました。会えますか?」と呼び出されたものです。
80歳代後半になっても声に張りがあり、眼鏡の奥がキラキラ光っていましたが、数年前に亡くなられました。平成22年8月に開かれた古希記念の同期会では、良い歳になった昔の生徒たちが、「勝村先生は怖かったなあ」と、いつものことながら口々に語り、面影を懐かしんだものです。
中学1年生になる春、父が高知市に転勤となりました。父は生命保険会社に勤めており、高知支社長に任命されたのです。妹二人を含め五人家族揃っての転居です。当時は今と違って、父親の単身赴任などは想定外のことで、私も合格した私立武蔵中学校を諦め、高知大付属中学校を受験しました。そのため、春休みに入って一人で汽車と連絡船を乗り継ぎ、四国山脈を縫うようにして走り、煤煙で真っ黒になって無事高知駅に着きました。過保護な時代ではありませんから、12歳の少年の一人旅を周りはさほど心配しなかったようです。当人も冒険旅行に胸をときめかしたほどですし、道中で隣り合わせた人もみな親切でした。
東京を発つ前のことですが、音楽担当の森木恵先生から、「土佐の空はローマのように青いよ」と励まされたことが忘れられません。高知に行ってはローマの空を思い描き、実際に会社の仕事で初めてローマを訪れた20数年後には、先生の言葉を噛みしめながら真っ青な空を仰ぎ見ました。子供心に夢を灯す先生とは本当に有難い存在です。
以上
連載第6回「龍馬の国」
中学生活は、昭和28年に高知市で始まりました。
町の中には水の澄んだ鏡川が流れています。学校は上流にありましたので、通学は土堤を自転車で走り、夏の帰校時には毎日のように青い淵で泳いだものです。坂本龍馬が遊んだ川です。
高知大学付属中では、国語の内田祥穂先生に課外授業で詩を教わりました。先生がガリ版で作られた最初の教材には、島崎藤村の「響きりんりん音りんりん」と題する詩が載っていました。皆で暗唱したのですが、七五調のリズムが何とも凛々しく響き、“馬は蹄をふみしめて故郷の山を出づるとき”という一節などは、青雲を遠く憧れる少年たちの心を奮い起こすに十分でした。藤村や北原白秋、さらには漢詩、漢文に生涯親しむようになったのは先生のお蔭です。
この頃から読書の楽しみを覚え、家の近所にあった貸本屋の本は読みつくし、小遣いをためて、毎月発刊される吉川英治の「新平家物語」を買いに行くのが楽しみでした。「君の名は」のラジオ放送が大変な人気で、その時間にはお風呂屋さんが空になったといわれた時代です。
写真は内田先生の筆墨です。二年生を終える時に、父の転勤で大分市に転校することになり、記念に書いて頂いたものです。持参した和紙綴りの冊子に「雲煙帳」と題をつけ、中には「香は禅心よりして火を用ふることなく花は合掌に開きて春に因らず」と、禅語のような難しい言葉を達筆で記されました。先生は中学生を子供扱いにせず、渾身の心をこめて書いて下さったことが、今にして良く分かります。
入学して念願の柔道を始め、学校代表で県や市の大会にも出場しました。武道との一生の付き合いの始まりです。土佐は柔剣道、相撲が盛んな武ばった土地柄で、学校の林の中で仲間と野稽古をしても、たまに胴着を下につけて通学しても、「ナンチャアナイ(何でもない)」という風でした。
この頃は毎朝5時に父に叩き起こされ、田舎道を数キロ走る日々でもありました。眠気との戦いでしたが、父のお蔭で本当に丈夫な身体を作って貰ったと感謝しています。
高知にはわずか二年しか住みませんでしたが、この地の気風はたいへん魅力があります。友人たちのイゴッソ風男ぶり、ハチキン風の女ぶりはいつも変わりません。きびきびして、台風一過の山の稜線にように、人柄の輪郭がくっきりしているのです。龍馬からこのかた多くの人物を生んだ風土は、今もなお健在だと思います。
以上
連載第7回「大分の日々」
昭和30年の春、この時も一人で高知市から大分市まで、汽車と船を乗り継いで、大分大学付属中3年生への転入試験を受けに行きました。
ところが、高松から大分行きの船に乗るところを、間違えて大阪行きに乗ってしまったのです。船長さんはじめ親身に心配して下さり、山陽本線回りの切符の手配など全てお世話になりました。汽車賃は後に親が払ったのでしょうか。大分駅に着いたのが早朝で、その日の試験に何とか間に合い、事なきを得たのは幸運というほかありません。それにしても、まことにのんびりした時代でした。
高校は上野丘高校(旧制大分中)に入りました。思い出深いのが、数学の村田三良先生と、歴史の後藤武彦先生です。
村田先生には数学ではなく、囲碁を教わりました。県のトップクラスの実力者です。日曜日になるとお宅を訪ね、四子を置いて対局しました。決して負けない先生で、切歯扼腕したものです。口三味線の名人でもあり、たいぶ煙に巻かれました。子供たちに顰蹙を買っている私の駄洒落は、この先生の直伝です。碁は小学3年生の頃に、父と大学生だった従兄弟の対局を見て覚えたのですが、向いていたのでしょうか、だいぶ熱中し今に至っております。
歴史の後藤先生には、世界史の面白さを教わりました。先生は逸話や裏話が得意で、その中の特大級がナポレオンのエルバ島脱出、パリ入城までの日に日に変わる「モニトール」紙の報道内容です。最初は「食人鬼巣窟よりあらわる」から始まり、パリに近づくにつれて表現が緩やかとなり、いよいよパリ到着の日には最高の英雄を迎える讃辞に充ち溢れていたという下りを、身ぶり手ぶりで語ってくれました。おまけに、かつて離反した将軍たちは足下に跪いて迎えたというのです。
必ず出典があるはずだと探し続け、ついに20年前に偶然神田の古本屋で見つけました。「フランス小噺集」(光亜新報社編、昭和32年12月刊)という、エスプリの効いた大人の読み物です。教室で聞いた直前に発行されており、そうだったのか先生、と一層親しみを覚えました。
大分では由布岳や鶴見岳への登山、久住山のキャンプ、霧氷見物、海水浴、海や川での釣りなど思い出深い健康な日々を送りました。後年就職することになった東芝の半導体工場が大分市に建設されたのも、広瀬勝貞知事と長野健大分合同新聞社長から「かぼす大使」に任命され、県のPRをお手伝いするようになったのも、深いご縁の賜物です。
以上
連載第8回「柔道との出会い」
柔道をやりたいと心から願ったのは、小学校6年生の時です。
餓鬼大将を争って一方の旗頭と砂場で闘い、ついに組み伏せられ、口一杯に砂を噛んだ悔しさが発端です。相手は一年前から柔道を習っていたのです。父親に骨の柔らかい内はダメだ、まだ早いと諭され、念願かなったのは高知の中学に入ってからでした。
稽古に励み段々と強くなるにつれて、喧嘩はしなくなります。中学2年生の時に空手の相手と一騎打ちしたのが最後です。顔は倍に膨れ上がり、親は誤魔化せても医者には一目で見破られましたが、相手も泥まみれで勝負は引き分けに終わりました。実力がつけば自信が生まれ、余裕ができ、自然に争わなくなるものです。発散したければ道場で存分にやれば良い、受け身を知らない弱い者を外で投げ飛ばすのは卑怯だと気づいたのです。柔道の創始者である嘉納治五郎師範の「精力善用、自他共栄」とか、「礼に始まり礼に終わる」など武道の精神性を学び、富田常雄の「姿三四郎」を愛読したことも役に立ちました。
大学に入ってからも、柔道部で稽古に励みました。対校戦では分け役ですから勝った覚えはあまりありませんが、生涯の友人がここで生まれました。師範の清水正一先生(八段・後の日体大学長)には、「負けて反省するのでなく、勝って反省せよ。日頃の工夫と精進次第だ」と教えられました。いつまでも心に残る言葉です。
後にアメリカの大学院に留学した時には、頼まれて柔道を週一回教えることになり、何と教授、学生男女200人が体育館に集まりました。私は「礼」を徹底しましたが、皆さんは柔道をタダで教わる代わりに、私のひどい英語を一生懸命直してくれたものです。ドイツ人、韓国人、日本人の有段者が助手として補佐してくれました。また、州の選手権大会に招かれ、主審を務めたのも懐かしい思い出の一つです。
就職した東芝では、柔道部長として選手強化に努めました。近頃は念願だった実業団リーグの一部に定着しはじめたようです。現在は、山下泰裕氏が主宰するNPO法人「柔道ソリダリティ」で創立以来の理事を務め、東京五輪後に創設された「講道学舎」でも20年来理事としてお手伝いをしています。
青少年時代には、心身の奥に棲みついた得体の知れない怪物が、突如として暴れ出すことがあります。どうすれば制御できるか中々の難問ですが、心の教育とあわせて、種目は問わずスポーツによる身体の鍛錬が欠かせないと私は思います。
以上
連載第9回「大学の恩師」
高校3年生になる時に、父が5年間の地方勤務を終え東京に戻りました。転校先は都立新宿高校です。一年間はひたすら、受験勉強の毎日となりました。
昭和34年に大学に入りましたが、教養学部の思い出といえば、担任の冨山芳正先生と60年(昭和35年)安保闘争です。先生は独語辞典を編纂された碩学で、文法を少しやっただけでエッケルマンの「ゲーテとの対話」を読まされました。昔の旧制高校はこうだったのでしょうか。「君たちが何人でも、酒では負けないよ」と言われるので、誘いあってお宅に押しかけ、奥様の手料理を堪能しました。飲むと「結婚式に呼べば、稀に見る秀才だったと言うよ」が口癖で、皆これ幸いと恩恵にあずかったものです。この頃の級友とは「無二会」という会を作り、今も夫婦揃って交流を続けています。
60年安保闘争は世情騒然、学生運動が最高のエネルギーを発揮した時です。学内の論争も活発でした。私は「一方的に破棄できないなら、改正した方が良い」と主張し、全学連の闘士たちにマークされたようです。とはいえ、70年安保とは異なり、学生同士がゲバ棒を振り回して、殺傷し合うような地獄絵がなかったのは幸いでした。
専門は法学部を選びました。石井照久先生の商法の最初の講義に出たとき、先生は新聞を読んでいる学生を見つけ、「君、新聞をしまいなさい。読みたければ教室を出なさい。そうでなければ講義はやらない」と言われました。その決然たる言葉に私は目が覚めました。冷やかし半分の寝ぼけまなこで様子を見にいった大教室ですが、それ以来お人柄にすっかり惚れ込んで1年半、珍しく欠かさずに出席しました。そして、卒業直前の最後の秋学期には、法学部長の先生が久しぶりに開いた少人数のゼミに採用して頂きました。それからは図書館に毎日閉館まで籠もりきって、真剣に勉強し、幅広く本も読み、遅ればせながら学問の一端に少し触れることができました。われながら、実におくてであったと思います。
先生ご夫妻には卒業した翌年、昭和39年秋に結婚の仲人をお願いしました。ゼミ生であったご縁でお引き受け下さったのです。記念のアルバムには、先生がマジックペンで描かれたウェディング・ケーキの絵があって、大事にしています。
昭和43年にアメリカ留学が内定した時にもご相談に伺ったら、「僕は古いから、若手に聞くといい」と言ってご紹介頂いたのが、中央大学教授で後に一橋大学教授となった津田真澂先生です。両先生ご夫妻とも実に仲睦まじいカップルで、お亡くなりになるまで、私たち夫婦は公私ともに終始ご指導を頂きました。
以上
連載第10回「異文化交流」
私の初めての外国生活は、昭和44年6月から二年間弱、米国ウイスコンシン州の首都マディソンで送り、産業関係研究所で労働経済学を学びました。
多くの友人を得ましたが、逃げ場のない異文化交流は寮生活にありました。
夏学期は湖畔の古い寮で、南部出身の巨漢、大酒飲みの黒人ビルと同室でした。その夏のアポロの月上陸は、ビルの持つ14インチ白黒テレビで見物しました。彼は寮で唯一のテレビの持ち主でしたから、部屋がはち切れるほど寮生が押しかけ、床やベッドに座り込み、国籍も肌の色も関係なし、重なるようにして大歓声また大歓声、世紀の偉業を喜びあいました。
秋からは新しい寮に移りましたが、同室者はユダヤ系のジョンです。富裕な実業家の息子で、毎日のように電話で株の売買をしていました。柔道でも「レッスン料を絶対取れ。俺がマネジャーをやる。儲かるぞ」と言い張るのには辟易しました。一蹴しましたが、金銭感覚が全然違うのです。子供の時からの家庭教育なのでしょうか。
次の春学期はフィリピン人の学者の卵エリー・ラモスで、後年フィリピン大学やハワイ大学の教授として活躍した男です。私も招かれて、ハワイ大学のシンポジュームで講演したことがあります。日本にも知己が多く、彼の夭折を多くの人が惜しみました。
2年目からは妻と子供二人も合流し、大学院生向けの家族寮に移り、丘陵を切り開いた湖畔の自然環境の中で暮らしました。また、夫婦揃って招かれる機会が増え、交遊範囲が飛躍的に広がり、海外生活をするなら家族同伴が良いとも実感しました。
当時最大の社会問題はベトナム戦争で、マディソンでも学生デモが頻発しました。その年の冬に母が来訪し、目抜き通りを歩いていたところ、目の前を長蛇のデモ隊がプラカードを掲げ進み始めました。車は道の反対側に駐めてあり、この寒さの中どうしたものかと思案していたら、和服姿の母が「皆さんご免下さいませ」と声をかけたのです。日本語の分かるはずのないデモ隊のリーダーが、何と「ストップ!」と大声で号令を掛け、我々家族が通る隙間を空けてくれました。母は両側にお辞儀をし、「皆さん有難う。ご苦労さま」と言いながら先導してくれました。一同あっけに取られた一幕です。
ベトナム戦争や人種問題で揺れていましたが、まだ豊かな良きアメリカの時代で、ホストファミリーをはじめ皆さんは本当に親切でした。私たちも帰国後はご恩返しの積もりで、途上国からの留学生を預かり、ささやかながらお世話を始めました。私たち夫婦を「お父さん、お母さん」と呼んだ一人は、今はガーナの外交官としてドイツで活躍しています。
以上
連載第11回「心にしみる土光さんの言葉」
昭和38年に東芝に入社して、最初に配属された職場が川崎市にあるトランジスタ工場(現多摩川工場)の総務部です。
それから二年経った昭和40年に、土光敏夫氏が社長に就任しました。明治29年の生まれですから、当時68歳です。古希寸前の社長と24歳の駆け出し社員。普通なら接点のあるはずがないのに、幸運にも私はその後お目にかかる機会にも恵まれ、直接間接に多くのことを学びました。人生の妙縁というほかありません。
土光さんは社長に就任するや、ただちに前線の視察を始めました。生産拠点の工場と営業拠点の支社、それに研究所などを、精力的にくまなく巡回しました。労働組合本部に一升瓶を下げて就任挨拶に行き、前代未聞のことと組合幹部を驚かせたのもこの時です。
私の居たトランジスタ工場にも、黒い煙を吐く車に乗ってお一人でやってきました。ここは集団就職で全国から集まった若い女子社員が多い工場です。現場視察の後で全従業員を体育館に集め、土光さんは訴えました。「力を合わせて会社の業績を良くしよう。皆さんは倍働いてください。私は10倍働きます」と。
その時の光景を私は生涯忘れることができません。十代後半の女子社員が、目に涙を浮かべるようにして聞き入っているのです。静かで力強いが、決して雄弁とはいえない言葉によって、何故これほど少女たちは心が揺さぶられたのだろうか。言葉は単なる符牒ではない、言葉の力はその人の総合力なのだ。隠しようもなく雰囲気に現れる人格、オーラのようなものが決め手であること、自分を磨かなければどうにもならないことを目の当たりに学びました。
私にとって、真のリーダー像を見た最初の場面でした。土光さんは有言実行の人で、毎朝7時には出社し、率先垂範精励し、下が順にこれに習い、社風が一変し、会社は確かな回復軌道に乗り始めたのです。
私にとっての土光さんは、どうしても明治維新の西郷隆盛に重なります。その共通点は、国を思う心、質素な生活、そして無私の精神です。その暮らしぶりは昭和57年にNHKで放映され、「メザシの土光さん」で有名になりましたが、辺幅を飾らず、高僧のように日々精進されました。教育者であった母上の教え、「個人は質素に、社会は豊かに」を守った一生だった、ともご自身が語っています。
一面では「怒号さん」と称されるほど怖かったそうですが、私たち若い者には常に春風のように接し、全社員の尊敬を集めたのです。
以上
連載第12回「会社再建の鍵は人の心」
昭和48年の初めから一年間、私は愛知県豊川市にある東芝の子会社、朝日木工(株)の再建に携わりました。
テレビの木製キャビネットを製造し、最盛期には三工場、従業員1500人を数えた会社が、当時は一工場100人程に縮小しておりました。労使関係が悪化し、労働組合は分裂し、市中に「東芝帰れ」などのビラが貼られていました。労働訴訟も頻発し、会社は解散か再建かの岐路に立たされていたのです。
労働担当であった私は、上司高瀬正二常務の指示で対策を検討しました。そして、解散案ではなく再建案をまとめ、土光社長に直接ご説明したところ一諾決裁を得ました。その後間もなく私は出向を命ぜられ、社長付として新社長の補佐役を務めたのですが、半年ほどで社長が急逝したため、暫くは孤軍奮闘を続けました。
徹夜交渉のすえ労組との和解が成立したものの、会社は聞きしに勝る荒れようでした。敷地は草ぼうぼう、建屋は落書きが一杯、窓ガラスは割れ、まるで廃屋のようでした。何よりも人心は荒れ、無関心と冷笑と諦めムードが支配していました。
何一つ思うようにはいきません。この時初めて餞に頂いた土光さんの言葉、「青草も燃える」の意味が分かりました。「夏草は水分を吸って重い。簡単には燃えないが、火力が強ければ一挙に灰になる。青草も燃えるのだ」。「うまくいかないのは君の火種が弱いのだ。相手のせいではない」と、怒鳴られた気がしました。早速私は布団を担ぎ、豊橋の寮から工場の警備室に移りました。少しずつ曙光が見え、社内にも確かな反応が現れ始めたのはそれからです。
皆の力で工場は綺麗になり、念願だった団体交渉での二つの労働組合の同席も実現しました。人心の安定がなければ、再建は画に描いた餅です。そこで三つの原則を作りました。約束を守ること、逃げないこと、ありのままに人を観ること、です。お客様や地域の方々も、会社の変化を好意的に見てくれるようになったと思います。
労使関係の悪化する原因の多くは、熟慮のなさや逃げ腰の姿勢など会社側にあります。労使関係は鏡ですから、経営者がまず自ら身を正すことが大切なのです。まして職場の人間関係が乱れては、会社の発展は期待すべくもありません。真剣勝負の再建の日々を通じ、その後の人生の礎となる多くのことを学びました。
後日談として。朝日木工は昭和54年に解散し、多くの人が音信不通になりましたが、職場の同僚だった白倉正彦君ら有志の肝いりで、平成22年11月に「皆で語ろう会」が実り、久しぶりに浜名湖畔のホテルに四十人が集いました。会社も組合もなく、往時を語り合って夜の更けるのを忘れたことです。
以上
連載第13回「野球部のブラジル遠征」
東芝野球部は昭和49年の秋に、初の海外遠征を行いました。
行き先はブラジルで、サンパウロ市を中心に各州の都市を巡ってほぼ一ヶ月、試合を重ねました。私は野球は全くの門外漢ですが、高瀬正二団長(東芝常務)と大館勲夫副団長(社会人野球協会副会長)の下につき、事務局の責任者として参加することになりました。
各地では熱烈な歓迎を受けました。バストス市は日本人移民発祥の地ですが、一行のバスが着いた夕刻、路上では爆竹が鳴り花火が上がり、皆目を丸くしました。新聞報道も毎日のように好意的な記事を載せ、単に野球だけでなく日本とブラジルの文化・教育の比較論にまで及んだのです。選手のマナーの良さが高く評価されたことは嬉しい限りでした。ブラジルの野球は主に日系人が担っています。この遠征がきっかけとなって、日伯の野球交流が盛んになったのは良い収穫であったと思います。
遠征チームにとって最も勉強になったのは、地方で日本人一世、二世の方々のお宅にホームステイをして、開拓のご苦労話を聞き、その大牧場や大農園を見学したことでした。ブラジルは巨大な国です。すべて桁が違うのです。一家の牧場や農園といっても、遥か地平線のかなたにまで広がっているのです。ある町では、近頃の日本の若者は国歌を知らないそうだがどうかと聞かれ、それなら論より証拠と、試合後のパーティが始まる前に、選手全員が揃って国歌を歌って安心してもらいました。
当時の野球部は監督が鈴木義信君(現日本野球連盟副会長)、コーチは小串正次郎君(現産業雇用安定センター理事長)が務め、チームを日本一にするため強いリーダーシップを発揮していました。私も一ヶ月の旅のうちに、どうやらカーブとスライダーの違いが分かるくらいには成長しました。
旅程の中で東芝の重電工場、石川島播磨の造船所を見学して、現地化への様々な苦心談を聞きましたし、団長のお供で政府高官を表敬し、民間外交の一翼を果たしていることを実感しました。また、サッカーの神様ペレにも会いました。サインボールを貰いましたが、紳士的な笑顔が魅力的だったと記憶しています。彼は現役最後の時を迎えており、その出場する試合を熱狂的なファンと共に観戦することができました。
当時のブラジルは、通貨は安定し、肌の色は様々ですが人種差別は少しも感じられず、治安は問題なく、夜の路上を夜学に通う若い男女が賑やかに歩いていました。国の安定には経済の安定が不可欠であることを、その後の南米社会の混乱が証明していると思います。
以上
連載第14回「東芝機械COCOM事件」
昭和62(1987)年は東芝の土台を揺るがした年です。
関連会社である東芝機械のCOCOM違反事件により、米議会は親会社の東芝を激しく非難し、議員が議事堂の前で東芝製のラジカセをハンマーで打ち壊すなど、情勢は一気にエスカレートしました。そして、7月1日の創立記念日には、佐波正一会長と渡里杉一郎社長が道義的責任を取って辞任し、会長は空席のまま、新社長に青井舒一副社長が就任するという、社員にとっては青天の霹靂の事態となったのです。
早速社内に対策チームが組織され、広報室長になったばかりの私もその一員に加えられ、数年間懸命に働きました。取り組みは当然ながら、事件の実態を明らかにするため第三者機関に調査させ、対外的に主張すべきは主張することが基本でした。ワシントンDCでは専門家を活用し、工場、営業所のある州では米人社員が中心となって草の根活動を展開しました。現地法人はアメリカの企業という理解が進み、また実状が知られるようになるにつれて、次第に世論や報道も沈静化し、感情的な制裁論が薄まっていったのは幸いでした。
私は同年の8月に渡米し、新聞雑誌の幹部と次々に会い、意見交換をしました。初対面にも拘らず、各社とも気持ちよく応じてくれました。主張した内容は、①東芝事件ではなく東芝機械事件だから、記事にもそう書いて欲しい、②罪なき親会社を罰するのはアンフェアだ、③会長・社長の辞任は法的責任ではなく道義的責任を取ったもの、という三点です。嵐のような質問を浴びせてきましたが、率直かつ公平で、留学時代に知った昔ながらのアメリカの良さが、今なお保たれていると感じました。
ウォール・ストリート・ジャーナルでは主筆はじめ論説委員長など数人のエディターに取り囲まれての議論でしたが、最後になって主筆が「子会社の独立性はアメリカでは理解されにくいが、罪のない親会社を罰するのは良くないと思う。君たちはどうか」と聞いたところ、一人ひとりが発言し全員が賛成しました。紙面からはすぐに東芝事件という表現は消え、東芝機械事件に統一されました。
アメリカの弁護士事務所と会計事務所など、第三者機関に依頼した調査結果は、その年の9月に纏まりました。東京とワシントンでの同時記者会見で発表しましたが、マスコミにこれだけの啖呵を切った以上、万一親会社も同罪と判定されれば、私の居場所はなくなるものと内心決めておりました。辞表を出さずに済んだのは、幸いというほかありません。
以上
連載第15回「コロンビア誘拐事件」
「事実は小説よりも奇なり」といいますが、間口広く事業を展開している企業には、思いもかけない事件が勃発するものです。
平成3(1991)年8月27日の深夜に、中南米のコロンビアで、出張中の東芝社員二名が拉致・誘拐されたのです。水力発電所の定期点検のため滞在しているところを、武装集団が襲ってきたのでした。現場近くの宿舎には銃を持った門衛がいたのですが、全く無力だったようです。
さっそく本社に対策本部が設置され、広報担当の私もその一員に加わりました。首都サンタ・フェ・デ・ボゴタにも対策チームが置かれ、広報からは三週間交代で課長クラスを派遣しました。拉致事件が頻発する国の内情や、救出の方途について知見の薄い会社にとっては、コロンビアの国を挙げての支援や、日本の外務省と在外公館、その他多くの専門家の智恵を借りながらの作戦でした。また、マスコミには解決まで連日のように、東京で私が記者会見をして情勢を説明しましたが、人命救助の観点で理解と協力を得たと感謝しています。幸い無傷のままで12月16日に救出するに至り、信頼して会社に全てを任せてくれたご家族に、安堵のご報告をすることができました。
救出成って現地で記者会見をする段になり、東京では固唾を呑むようにしてテレビに見入りました。年かさの中山明美技長(写真)が述べた、「必ず会社が助けに来てくれると信じていました」という言葉には、思わず大歓声が上がりました。簡易ベッドを持ち込み、交代で宿直を続けてきた広報担当の一同は、苦労が報われたと皆で手を取り合って喜び合ったものです。後日談ですが、二人は不自由なジャングルの奥の幽閉に耐え、会社による救出作業が進んでいることを信じ、軽挙を戒めあい、粗末な食事も残さずに食べ、ひたすら自己管理に努めた日々だったそうです。
この事件は、会社と社員との関係を考える良い機会になりました。無味乾燥な「契約関係」だけではなく、人間的な深い「信頼関係」が元にあること。そこに日本の会社の最大の特色と強みがあり、会社発展の鍵があります。もちろん約束事は文書にし、お互いにそれを守るのは当然のことですが、「書かれざるルール」を大事にする気風が失われたとき、職場は荒れ始め、企業体の進路が揺らぎだすのでしょう。
従って経営者は、人間関係を重んじ、「社員を守る」という覚悟を、常に徹底して持たなければならないと思うのです。
以上
連載第16回「イギリス生活」
平成7(1997)年から2年弱でしたが、ロンドンに駐在しました。
東芝の欧州総代表と、着任後に地域統括会社として設立した東芝ヨーロッパ社長を兼務した日々です。ブレア政権の誕生、バーミンガムサミット、ダイアナ妃の事故死、両陛下の訪英、ユーロの導入など歴史的な出来事が続きました。
ダイアナ妃がパリで交通事故死した事件は最もセンセーショナルでしたが、翌朝のテレビの路上取材に答え、ブレア首相が“ピープルズ・プリンセス(国民の妃)”の死を悼む、と述べた言葉が印象的でした。妃の言動については英国内にも賛否両論がありましたが、この一言で世論は落ち着きを取り戻したと思います。一国を指導する政治家の洗練された言葉の重さは、付け焼き刃でも軽い思いつきでもない、長年の鍛錬を確信させるものでした。葬儀の当日は、バッキンガム宮殿の前にエリザベス女王が一人たたずみ、葬列を見送っている姿が心に残りました。
在任中に国会の公聴会に招かれたことがあります。
平成11(1999)年からのEUのユーロ導入に対し、英国は不参加を決定しましたが、それによって外国資本の直接投資が減少するのではないかと、下院の貿易小委員会が日本企業の意見を聴く公聴会を開催したのです。たまたま私は日本人商工会議所の役員をしていたので、製造業の代表として、他に三井物産、三菱銀行の現地責任者と共に出席しました。英国に投資してきたメリットを語り、「なるべく早いユーロ参加を望む。それまではポンドとユーロの関係を安定させる必要がある」などと、率直な意見を述べたのですが、オニール委員長はじめ謙虚な姿勢で熱心に耳を傾けてくれました。その後林貞行大使の設営で、日本大使館で議論の続きが行われ、民間経営者に聴こうとする、政治家の真剣な姿勢を肌で感ずることができました。
東芝の現地法人は欧州内に27社ありましたが、それを束ねるため共通言語の英語化を一層徹底し、会計単位をユーロに改め、異文化交流を深め、国境を超えた欧州労使協議会(EWC)も軌道に乗りました。英語による統一化では、東京本社とのコミュニケーションが日本語だったことに違和感を感ずるほど、かなり速いスピードで進んでいました。
EWCでは日本の労使協議会と同じように、情報を公開し、オープンで活発な意見交換に努めました。対立的労使関係が一般である欧州流ではなく、信頼関係をベースとする日本流の導入です。各社労使代表とも当初は多少勝手が違う風でしたが、っすぐに違和感は消えたようです。相互理解のプロセスには、国の違いはあまりないと思えてなりません。
以上
連載第17回「日経連の精神」
長年勤務した東芝を退職し、平成11(1999)年初に日本経営者団体連盟(日経連)の事務局に入りました。
わが国の経済・社会はバブル崩壊後の混乱が続いており、「失われた10年」と呼ばれた状況を何とか打開できないものかと、国レベルでの方策を模索しました。中でも雇用と労使関係の安定、社会保障制度改革、ILOを通じた国際戦略などに力を注ぎました。国の社会保障審議会や労働政策審議会の委員としても、多くの課題に取り組みました。
その年の5月の総会で、日経連の会長は根本二郎氏から奥田碩氏に替り、やがて平成14年には日経連と経団連とが合併して、新しく日本経済団体連合会(日本経団連)が誕生し、初代会長に奥田氏が就任しました。時代の流れというものでしょう。こうして平成18年に退任するまでの7年余、私は経済団体の事務局役員として奥田会長のもと、のびのびと仕事をさせて頂きました。
奥田氏は日本経団連の会長に就任して、「人間の顔をした市場経済」「多様な選択肢を持った経済社会」の構築を提唱しました。市場の弾力性を高め経済を活性化しつつ、雇用を大切にし、敗者復活の道を開き、多様性を尊重する社会を目指そうとする構想です。「人間の顔をした市場経済」は、この年の世界の流行語となり、その後期せずしてクリントン大統領はILO総会で、金鐘泌韓国首相は来日時のスピーチで同じ趣旨の発言をし注目されました。
日本経団連は毎年初に「経営労働政策委員会報告」を発表します。近年は春季賃金交渉方針だけでなく、企業の経営政策全般について提言してきました。全国各地への説明は手分けしますが、私は関西と中部の経営者協会には毎年のように招かれ、皆様と交流することができました。政策提言はあらゆる分野に及んでいるため、特に地方の経営者からは当年度の経営指針として尊重されています。創刊以来40年に近い積み重ねの賜物であると思います。この間、雇用では連合と協議して「雇用宣言」を発表し、それが発展して政労使三者による「雇用協定」や「ワークシェアリング協定」が纏まりました。社会保障制度の改革では、日商、同友会などと連携し全国決起大会を開き、決議事項が三団体の長から総理に提出されたこともあります。
企業経営の基本ということでは、私は昭和23年の日経連の設立宣言をいつも思い出します。戦後の大混乱期に、「経営者よ、正しく強かれ」と呼びかけ、「人間尊重の経営、長期視点の経営、経営道義の高揚」を掲げた志の高さに打たれます。常に新鮮であり、現代の心ある経営者にも訴えるところが大きいと思います。
以上
連載第18回「ILOを通じた国際交流」
ILO(国際労働機構)の活動には、私は若い頃から関与してきました。
初めてジュネーブの年次総会に日本使用者代表団の一員として参加したのは、昭和55(1980)年のことで、二年がかりで「家庭責任を持つ労働者の男女均等待遇」についての条約を作りました。一人で全部任されましたので、堂々巡りの議論を果てしなく繰り返し、妥協に次ぐ妥協の産物としてやっと最終案が纏まり、最後に大会議場で賛成投票のボタンを押すまで、一部始終を体験しました。能率ではお話にならない低レベルですが、国連関連の会議の論議がいかなるものであるかを知る上で、得がたい体験であったと思います。
その後時折アジア・太平洋地域会議などに出席する機会がありましたが、本来業務として取り組むようになったのは、平成11(1999)年に日経連勤務となってからです。ILOも大きな変わり目に来ており、前年の平成10年には、歴史的な「労働における四つの基本的基準」についての宣言が採択されたばかりでした。提案は使用者側が行い、政府・労働代表の全面的賛成を得て成立しました。強制労働、児童労働、差別待遇を禁止し、結社の自由を守るという内容ですが、この四基準は後に国連の「グローバル・コンパクト」やOECDのガイドラインにも取り入れられ広く国際的に認知されるに至るのです。平成11年には児童労働に関する新条約が成立し、四基準を支える八つの条約が確立しました。第一次大戦直後に生まれたILOの歴史の中でも、記念すべき変革が実ったと言えます。また、国連の一機関である以上、労働問題も国際政治情勢と切り離すことができず、ミャンマーの強制労働をめぐる問題をはじめ、デリケートな問題に悩まされることもありました。
アメリカに次いで二番目という分担金の大きさに比べて、ILO事務局で働く日本人職員の数が余りに少ないのが長年の課題です。機会は十分あるので、国際舞台で活躍する志を、特に若者たちに持って貰いたいと思います。
私は毎年三回はジュネーブに通いました。春秋の理事会と夏の総会です。ここで、日本の政府・労働代表だけではなく、各国の代表やILO職員との交流を通じ、多くの友人知己を得ました。根回しも盛んに行われますし、会議前の少人数による実質的な論議など、物事の決まるプロセスは洋の東西を問わず良く似ています。便利なメールが普及するにつれてコミュニケーションが容易になりましたが、大事な物事が決まるのは、顔つき合わせての交渉の場であることに変りはありません。会議や文書の最終結論に影響を与えられるかどうかは、背景となる国力や肩書以上に、交渉当事者の力量、見識と人間性、周りからの信用に負うところが大きいことを実感します。
以上
連載第19回「アジアに経営者団体を設立」
日本はアジアの国々ともっと連携を強める必要があります。
大きな会合に時折参加するだけではなく、恒常的な場を設けることはできないだろうか。そうすれば日常的なコミュニケーションを通じて親交を深め、必要があれば国際社会に向け統一した意見を述べることもできるのではないか。色々と考えた末、奥田会長の賛同を得て、アジア太平洋地域に経営者・経済団体の連合組織を設立することを計画しました。
各国との個別協議を続け、賛同を得るまでに二年弱かかり、アジア太平洋経営者団体連盟(CAPE)の設立総会を、平成13(2001)年にバンコックで開くことができました。会長には奥田さん、副会長はパキスタンのアシュラフ・タバニさん(故人)はじめ豪・韓・比の代表、事務局長には私が選任されました。設立総会にはILOのソマビア事務局長も出席し、門出を祝ってくれました。当初の参加国は日、中、韓、印、豪、ASEANなど17カ国で、間もなく21カ国となり現在に至っています。アジア太平洋地域には労働組合の地域組織もありますので、定期的に意見交換の場を設けています。平成22年から会長と事務局は、日本の手を離れマレーシアに移ったと聞いています。
CAPEの憲章には目的として、「ビジネス環境を整え、社会・経済の発展に寄与する」と記しました。上部団体を持たない独立団体ですが、APECではなく、ILOの枠組みを尊重し組織化しました。ILOにはオブザーバーとして認知され、アジア生産性本部(APO)とも友好関係を結んでいます。また、団体長サミットを三年に一回各国持ち回りで開催してきました。これは日経連の鈴木永二会長時代、昭和63年に創設された「アジア・太平洋地域経営者サミット」を発展させたものです。CAPEは、こうした先人が耕した素地があったからこそ生まれたと言えます。
2国間関係では日中産業シンポジュウムがあります。根本二郎会長時代の平成8年に、中国企業連合会の袁宝華会長と合意して、中国で第一回が開催されたのが最初です。その後日中交互に毎年開かれてきましたが、平成19年に終息したと聞いています。
今から10年近く前のことになりますが、シンポジュウムが大連で開催された時に、一行と共に瀋陽に向かう列車の窓から眺めた、夕暮れの光景を忘れることができません。地平線に沈む、真っ赤なお盆のような太陽です。かつて祖父や父が見たに違いない光景を味わうことができ、まことに感慨無量でした。
以上
連載第20回「労使自治の精神」
私は長く労使関係に従事しましたが、その重要性に目覚めた出来事が二つあります。
すでに記した子会社の再建と、第一次石油危機後の労使の対応です。前者は企業というミクロの場での経験で、職場の人間関係が乱れていては、決して会社は発展しないことを骨身にしみて学びました。労使関係の原点といえます。
昭和48(1973)年の石油危機はマクロ経済の大問題で、物価の超高騰を招き、トイレットペーパーが店頭から消える騒ぎになりました。インフレ下の不況、スタグフレーションが襲いかかってきたのです。先進国に共通する問題でしたが、わが国がいち早く他国に先駆けて成長軌道に戻ることができた理由は何であったのでしょうか。
それは、労使の当事者が良識をもって国と産業と企業の将来を考え、長期的視点で適正な賃上げの着地点を見出したことによるもの、と私は思います。いわば、「労使自治」の成果です。日経連が昭和48年に「大幅賃上げの行方検討委員会報告」を纏め、広く社会に訴えたのもその一環でした。今の「経営労働政策委員会報告」の前身です。欧州では政府主導で賃金抑制をする「所得政策」によって事態を収拾しようとしましたが、労使当事者の反対によりいずれも成功しませんでした。
昭和50年春の労使交渉は、天下分け目と言われるほど厳しいものでした。電機産業も例外ではありませんでしたが、昭和51年春に鉄鋼・自動車・造船と歩調を合わせ、初めて「集中決着・一発回答・平和解決」という、いわゆるJC路線が実現しました。前年の激しい交渉を経て、各社労使トップがこれではならじとした英断の賜物であり、私も一労働課長として下働きをし、感無量で妥結の日を迎えました。
その昭和50年、労働運動の指導者であった太田薫氏が、「春闘の終焉」(中央経済社)を出版し、この年の春闘を論じ、労働側の挫折であったと評しましたが、率直なところ強い違和感を覚えたことを否めません。何故なら、労使が苦心の末に到達した結論に、勝った負けたはないと思うからです。会社の存続や従業員の生活を守ろうとするならば、労使は決着したところを始発点に、明日に向かって協力することが欠かせないと思うのです。
労使自治の精神を忘れ、自ら汗することを二の次にし、解決の方途を他に求めるようになれば、社会は自律安定力を失うでしょう。かつて、東芝の労働担当専務であった河原亮三郎氏が、「最高速回転の独楽は止まって見える。労使関係も同じだ」と喝破した言葉を思いだします。
以上
連載第21回「お客様を第一に」
NEXCO中日本に着任したのは、平成18年6月末の株主総会でした。同年5月に日本経団連を退職した直後です。
日本道路公団の民営化に伴って、民間から会長CEOを招くことはお国の方針とはいえ、社内の皆さんはどう受け止めたでしょうか。初対面で気心も知れず、道路造りの経験もない者に、したり顔でかき回されてはたまらない、という心配が必ずあるだろうと思いました。人情の当然です。同じトップ人事でも、自社出身者が輿望を担って登場するのではないのです。そこで、私が心に決めたことは、知ったかぶりは一切やめ、先入観念を捨てて虚心坦懐に、良かれ悪しかれ実情をありのままに把握することでした。人心の掌握が最も大切であり、その上でしがらみなしに客観的に、正しいと思う施策を決めても遅くはない、回り道のようでも、かえってそれが一番の早道だと考えました。
就任の日に、私は全社員に直接メッセージを伝えました。
民間会社に共通する日常業務に欠かせない基本姿勢を述べたのです。それは、①お客様を第一にする、②衆知を集める、③現場に立って考え行動する、④変革を続ける、⑤約束を守る、の五つです。一つひとつを取れば、どれも目新しいものではありません。お客様第一となれば他は第二以下であること、風通しの良い職場を作って、社内外の衆知を集め、とことん現場主義に徹し、時代に遅れぬよう改革を継続して民営化の実を挙げ、約束は昔の口約束でも必ず守ろう、などと強調したでしょうか。
この当たり前のことを、日々たゆまず実行し、迷ったらこの五つの原則に戻ろう、私も先頭に立ってやると明言しました。その後間もなく前線の巡回を始め、現場を見学して実物に触れ、社員一人ひとりとの直接対話に入りました。そして、在任中の四年間あらゆる場所で、「またか」というほど繰り返し語り続けました。
本号からは四年間の経験を綴りますが、企図の実現は大方道半ばです。
生まれたての企業は人の若々しい青少年時代に似て、現在進行形が最も健全な姿だと思います。企業の永続性を願うのであれば、ちょうど駅伝と同じように、選手が襷を引き継いで走ることが大事です。企業は駅伝と違ってゴールはありません。目先の成功などは小事で、全て将来への一里塚だと考えればよいと思います。皆で考えた施策を、皆で大きく実現して貰いたいと、将来に期待しています。
以上
連載第22回「高速道路のおかげで助かりました」
現場を回り始めて間もなく、平成18年7月に長野県を集中豪雨が襲い、土砂崩れが発生しました。
私は早速中央道の被災現場に入り、終日復旧作業を見守りました。諏訪湖辺は山肌から高速道の下を通って土砂が流れ落ち、数名の死傷者が出る惨事となりましたが、橋脚が勢いを二分したこともあり被害は拡大しませんでした。
一方、伊那谷の駒ヶ根付近では、山から流れ落ちた大量の土砂、岩石、裸になった木々が高速道を埋め尽くしており、飯田市にある当社保全・サービスセンターが中心となって、大勢でキビキビと復旧作業を行っていました。当社社員の出動は当然ですが、当時社会問題化していたファミリー企業も、地場の企業体の皆さんも、災害発生と同時に自発的に現場に急行し復旧にあたっていたのです。
この時、農家の主婦から「高速道路のお蔭で助かりました」と言われたと、泥まみれの作業員が嬉しそうに語ってくれました。山裾を走る中央道が土砂流を止めたため、反対側に広がる畑や農家に被害を及ばなかったというお礼の言葉です。私にとっても、社会インフラのもつ意義をこれほど分かりやすく教えてくれた言葉はありません。
NEXCO中日本は大変な強みを持っている会社だ、と私は確信しました。それは世間に誇り得る「強い現場力」です。現場力とは、問題が起こった時にすぐに解決できる能力で、「使命感+チームワーク+技術力+経験」の総和と私は考えています。一朝一夕に出来るものではなく、長年かけて築き上げられた無形の財産です。高速道路の建設に着手して数十年、ここに最も優れた誇り得る伝統が蓄積していることを目の当たりにし、大変心強く思いました。
この日、私は会社の将来のために二つの決心をしました。一つはこの強み、底力を徹底的に伸ばすことです。会社の発展は欠点を直すだけでは不十分で、長所を伸ばすことから始まるからです。もう一つは、ファミリー企業の子会社化のスピードアップでした。当時は子会社化に5年かける構想で動き始めていましたが、関係者の尽力により3年前倒しし、2年で完了することができました。道路の維持管理のために必要不可欠なら、100%子会社化して、社長も派遣し、名実ともに一体で仕事を進めればよいのです。かつてのファミリー問題の一因は、けじめを曖昧にしたところにあったと私は思います。
以上
連載第23回「天災はやむをえないが、人災は起こさない」
災害は忘れた頃にやって来るといいます。社会インフラを担う事業者として、天災を忘れることはありません。しかし予測の難しさにはいつも悩まされました。
台風や大雨は気象情報を解析して備えますが、災害発生の場所まで特定するのは難しい。まして大地震となれば、十年単位の時間幅と広い地域で「そろそろ起こりそうだ」とする位が、予知としては精一杯のところです。心は「治にいて乱を忘れず」であっても、打つ手には限度があるのです。
人知を超えた世界にいかに向かい合うか。悩ましい限りですが、高速道路会社には二つの使命があると思います。一つは、過去最大級の地震や雨にも耐えられる道路を造り、日常のメンテナンスを手抜きせずしっかりと続けることです。二つは、災害が発生した時には、安全・安心の確保を第一義に、なるべく早い復旧を行うことです。
平成21年8月に折からの豪雨と地震が重なり、東名高速道牧之原地区で路肩が崩落しましたが、復旧作業は道路会社の社会的使命を果たす場と考え、即時に決めた方針は次の三つです。
一つは、天災はともかく人災は絶対に起こさない、すなわち二次災害は決して発生させない、そのためなら開通時期が遅れてもやむを得ない、二つは、災害原因と復旧作業については洗いざらい全てを公開する、一切隠し立てはしない、三つは、原因は外部専門家による第三者委員会で究明し、直ちに管内全域の類似箇所を調査し必要な手を打つことでした。これらは全て愚直一途に実行されました。
幸いにして、8月11日に始まった通行止めは仮復旧を終えた15日深夜に解除し、お盆の帰省ラッシュに間に合わせることができました。地元をはじめご関係の皆様のご協力の賜物です。当社の強みである現場力も発揮できたと思います。作業が広く報道されたこともあって、数多くの激励の手紙が寄せられました。開通直後の16日未明には、川勝平太静岡県知事から感謝と慰労の手書きのファックスを頂きました。これらの暖かい激励文は、全社に回付しましたが、不眠不休で取り組んだ一同のやる気をいっそう高めたことは、申すまでもありません。
本復旧には一年ほどかかりましたが、それまでには類似する380カ所の点検を全て完了し、安全を確認し、今後の対処方針を明確に決め、全社に徹底することができました。
以上
連載第24回「現場での意見交換会」
NEXCO中日本には、四支社とその傘下に建設工事と維持管理を担う現場事務所が四十数カ所あります。
それらを個別訪問し、現場をつぶさに視察し、全員を集め一人ひとりの意見を聞き、私も遠慮なく考えを述べる「意見交換会」を開きましたが、有意義だったと思います。終わった後は、割り勘で会食懇親の場に移りましたから、一カ所で数時間をともに過ごしたことになります。元気の良い頼もしい集団であることを実感し、今後の改革に確かな手応えを覚えました。
社員は問題の大小と男女を問わず、真正面から真剣に疑問をぶつけてくれたと思います。会長が出向いて、説教ではなく意見交換をするなどは、よほど珍しかったのでしょうか。良い意見はすぐに実行させましたが、本社に持ちかえってルールから検討し直すこともしばしばありました。
しかし、私一人がどれほど頑張っても、現場で直接意見を聴く機会は、年に一、二度が精一杯です。そこで、平成から問題点が発掘できるようにするため、本社から現場までの風通しの良い職場造りを急ぐことにしました。例えば、キャラバンと称して本社スタッフが手分けして現場に出向き、意見を聴くなどの取り組みが始まりました。
忘れられないのは、最初の巡回の時に、聞いた大変ショッキングな意見です。四十歳前後の社員が、一年前の民営化の頃を振り返りこう述べたのです。「私の妻は外出拒否になりました。買い物にも出ないのです。理由を聞いたら、あなたの旦那さんはひどい会社に勤めていると言われたというのです」と。別の社員は、「自分の小学生の息子は登校拒否になりました。お前のお父さんはとんでもない会社に居る、と虐められました」と話してくれました。日本道路公団は民営化の当時、橋梁談合やファミリー企業問題などを盛んに報道されていましたので、社員やその家族はよほど肩身の狭い思いをしたに相違ありません。自分だけならともかく家族までもが、という率直な父親の訴えを聞いて、その苦しみをよく理解することができました。
ここで私は、就任の時に仕事を進める心構えとして述べた、お客様第一などの「五つの基本姿勢」だけでは足りない、社会との関係において会社が目指す将来像を、はっきりさせる必要があることに気づきました。
そこで、決まったのが「良い会社で、強い会社」という目標です。「良い会社」とは世の中から信頼され喜ばれる会社で、社員も家族も胸を張って誇れる会社、「強い会社」とは適正な利益を上げ続けることのできる会社です。「五つの基本姿勢」は目標達成のための手段と位置づけ、平成18年10月に公表しました。
以上
連載第25回「経営理念の制定-「言葉の力」による求心力」
民営化の過程で世間から徹底的に叩かれ、元気をなくしている集団に、どうすれば自信を取り戻させることができるか。
これが平成18年に着任した当時の最大の課題でした。現場を回り、社内外の多くの人に会い、意見を聞きながら考え続けた上での結論は、ばらばらになりかかった会社に「求心力」を築くことでした。
太陽系が引力と遠心力によって軌道の安定を保っているように、企業も確固とした引力の中心が必要です。実力と自信のある経営者なら、「俺について来い」と、自分自身を求心力にして全体を纏めようとするのでしょう。しかし、私のように創業者でもなく、尊敬を集めている訳でもなく、突如外部から舞い降りてきて、しかも平凡な力量しかない者が求心力になりえないことは、あまりにも明瞭でした。
そこで、普遍性のある「言葉の力」を求心力としてはどうかと考えました。よほどのことがないかぎり、人や環境が変わっても変わることのない、不易の「経営理念」の策定です。「言葉」は、人が変わり時を経ても残ります。創業の精神とも言えるでしょう。そして、ひとたび決まればトップ以下全員がそれに従う、私も組織の一員として率先実行することにしたのです。
すでに「五つの基本姿勢」を平成18年6月に、「良い会社で、強い会社」を目指す企業像を10月に発表しました。これを素材に翌年1月から、新中期計画の策定作業の中で経営理念の検討がなされました。この中で、道路事業の社会的役割として、「安全・安心・快適」を徹底的に追求することも明らかにしました。各職場の衆知を集めて論議し、結論が纏まり、経営会議や取締役会の議を経て、平成19年4月に社内外に公表しました。
トップが構想やヒントを与えることは重要ですが、会社の基本方針を決めるには、トップダウンだけではだめです。できるだけ多くの社員の参加と共鳴が必須です。そして、ひとたび全員の共有財産となった以上は、単なるスローガンではありませんから、改定する場合にはよほど慎重なプロセスを踏む必要があるのは当然です。
あらゆる組織には、変えてはならないもの(不易)と、変えなければならないもの(変易)とがあります。NEXCO中日本は、原理原則(プリンシプル)を示す経営理念は不易、臨機応変を要する経営施策は変易で行くことにしました。プリンシプルを失った企業は漂流するしかないと思います。
以上
連載第26回「目で見て、手で触れて、心で聴いて」
四年間の在任期間中に、私はおよそ五十カ所の前線拠点をもれなく巡回し、意見交換を重ね、数えれば五周目の途中まで進みました。建設や維持管理の現場、休憩施設などは、お客様の案内を含めて数え切れません。このことを通じて多くのことを学びました。
就任時は新米の会長に対して、本社のスタッフによりレクと称する概況説明が連日行われました。悲しいかな、予備知識のない者には猫に小判で、粋をこらした第一級の説明も本当の価値が分かりません。情景すら目に浮かばないのですから。後にスタッフに漏らして大笑いになりましたが、「こりゃあ蒸留水みたいなものだ。完璧な水には違いないが、私には味がしない。まず現場に行って、色も香りもある水を飲んでみよう」と思い立ちました。
三ヶ月かけて一回目の巡回を終えた頃の嬉しい発見は、会議で言葉が通じ始めたことです。よほど難しい専門用語は別として、通常の意思決定に必要な語彙は多少身についたのでしょう。現場の光景が目に焼き付いており、話が早くなったこともあります。
コンクリートの損傷など老朽化の進行は、目で確認し、触ったり叩いたりしてみなければ分かりません。軟弱地盤は実験盛り土の上に立って沈下の程度を確かめ、土砂崩落や交通事故の悲惨さは直後の現場に立ち会って、工法の新工夫など現代工学の粋は橋やトンネルなど構造物の裏を覗いて、トンネルの空気の汚れは排気口に潜り込んで、トイレの悪臭は立ち寄ってみて、人の思いはじかに聴いて、初めて分かるものであることを実感しました。机上論では限界があって、情理の行き届いた問題の解決などは到底できないと思います。
特に貴重だったのは、社内外の多くの方々から率直な意見を聴けたことです。会社方針の決定にあたり、最も大きな示唆を受けました。現場主義とは、本社に現場の人を呼びつけて報告を聞くことではありません。自ら足を運び、目で見て、手で触れ、心の耳で人の話を聴き、自分の頭で徹底的に考え抜くことだと思います。そうして初めて、眼光紙背に徹する実力が身につくのではないでしょうか。
物事は全てを予測することはできませんから、何か起こったときに早めに手を打つことが大切です。良い目にはすぐに水をやり、悪い目は早めに摘み取ることが、明日の良い結果に繋がるのです。現場には経営のためのあらゆるヒントが埋まっていると私は思います。
かつて土光さんが足繁く現場を訪れ、現場主義に徹した思いの一端に触れ、その爪の垢を煎じて飲んでみようと、及ばずながら私の現場主義を実践し続けました。
以上
連載第27回「企業の社会的責任」
世に不祥事は尽きません。
目先の利益や世間体に目が眩み、発端となる細事を見過ごし、ついには破綻したケースが多いようです。しかし、赤字続きでは、会社は潰れる外ありません。どうすれば社会から信頼される「良い会社」で、しかも適正な利益を上げる「強い会社」にすることが出来るか、が当社の課題でした。
適正な利益を得ない限り、将来への投資、お客様サービスの向上、社員の福祉などあらゆる施策は、絵に描いた餅に終わります。企業経営のイロハですが、民営化の当初は利益観念の希薄さが気がかりでした。公共事業は社会奉仕だから利益を上げる必要はないとし、一部には儲けることに対する罪悪感さえありました。しかし、株式会社にとって、利益はサービスに対する正当なリターンだ、という考え方が急速に浸透し、それなりに官業意識からの脱皮が進んだと思います。
企業の社会的責任(CSR)の元には企業倫理や遵法があります。市民社会の当然の義務ですが、CSR経営を通じて、この義務として「しなければならないこと」にとどまらず、世の中のために積極的に何を「することができるか」を求めたい、と考えました。
その結果、平成19年に「環境報告書」を発表し、翌年からは衣替えして「CSR報告書」を毎年世に問うことにしました。環境問題を核にしつつ、顧客、国民(株主)、地域社会、取引先、従業員など幅広いステークホールダーのために何ができるか、という観点で編集し、会社の施策として進んでいる点も、遅れている点も掲載してきました。独りよがりを避けるために、外部有識者による「環境懇談会」、後に改称して「CSR懇談会」(座長:奥野信宏中京大学教授)が設立されました。委員の先生方にはしばしば現場視察をお願いし、広い視野と専門性に基づく率直な意見を頂き、それを反映して最終の「CSR報告書」を作成しています。また、国連のアナン事務総長が提唱した、「グローバル・コンパクト」にも加入し活動をしています。
CSRは日々の事業活動の隅々にまで埋め込まれ、一人ひとりが体現するのでなければ本物ではありません。CSRは事業そのものであって、決してアクセサリーではないからです。寄付をしたり地域のイベントに参加するのは大事なことですが、CSRのほんの一部の側面にすぎないのです。
日本には古来、例えば近江商人の「売り手よし、買い手よし、世間よし」という「三方よし」の思想など、企業の社会的責任を実践してきた原型があります。大いに参考にし、活用したらよいと思います。
以上
連載第28回「飛騨トンネルの開通に感激する」
飛騨トンネルは全長10.7km、世界有数の長さです。
平成19年1月に貫通、平成20年7月に飛騨清見と白川郷の間25kmが開通しました。そのうちトンネル部は10本で20.7kmに及び、最大のものが飛騨トンネルです。着工から36年を経て、東海北陸道185kmが全線開通したのです。待つこと久しかった、太平洋と日本海を直結する高速道路の完成です。しかも、北陸道と繋がることによって、高速道路がループ化し、中部圏に新たなネットワークが生まれたのです。
飛騨トンネルの貫通には、計画を超える10年弱の歳月を要したのですが、その原因は籾糠山の軟弱地層と大量の湧水でした。湧水量はピークで毎分70トンに達しました。これは人口30万人の都市の上水道1日分をまかなう規模です。また、土かぶりといって、山の上からトンネルまでの厚みが千メートルという地形での工事であり、最新鋭の超大トンネル・ボーリング・マシン(TBM、写真)も不良地山に遮られ一歩も進めない状態が続きました。
最後の壁が貫通すると、戦い終えた満身創痍のTBMが塵煙の向こうに姿を現し、冷たい空気が流れはじめます。感動の瞬間でした。
この間一人の死亡事故も発生しなかったのは、関係者の努力の賜物です。高い安全意識に加え、工法の発達も大いに貢献しましたが、小説や映画にもなった黒部ダムに匹敵する難工事でしたから、高く評価される価値があると思います。今後の課題は、対面交通である長大トンネルでの安全の確保です。同じように対面交通で仏伊間のアルプスを貫く11.6km余のモンブラントンネルが、1999年に死者39名、負傷者27名の大惨事を起こし、3年間閉鎖された事故を忘れてはなりません。
東海北陸道は線として繋げることを先決に工事が進められましたが、今後は安全のために、完全四車線化が地元や産業の要望として高まってくると予想されます。
東海北陸道の完成は、経済・社会両面の日常を大きく変えました。白川村の谷口尚村長は、「これで高校生が高山市に下宿しないで済む」と語っています。7人(現10人)の生徒が村の用意したバスで通学を始めました。通行料金は無料サービスをしています。救急病院も近くなりました。話題性の高い年間七千億円と推定されるマクロ経済効果に比べれば、小さな出来事に見えますが、家族やコミュニティにとっては革命的ともいえる大きな変化が起こったのです。
以上
連載第29回「点から線へ、線から面へ」
在任中の四年間に、幸いいくつもの高速道路の開通に立ち会いました。
東海北陸道の全線開通のほか、新名神、紀勢道、東海環状道、中部横断道、圏央道などの部分開通があります。道路が町と町を結んで点が線になり、ネットワーク化して線が面となった時に、劇的な変化が経済・社会に起こることも目の当たりにしました。
昭和31年にワトキンス調査団が来日し、「日本の道路は信じがたいほどに悪い」と言わしめた状況は、その後の経済発展とモータリゼーションとともに一新しましたが、これで十分かどうかは、長期視点に立ち公の場でもっと論議されてよいと思います。
必要な高速道路は何かを考える場合に、参考になるのが欧米の道路政策です。私は欧米に住み、自分でも運転して各地を走り回りました。まさか将来道路会社の経営をやるとは思いもしませんから、あくまでもドライバーとしての感想ですが、道路に対しては日本と欧米ではかなり考え方に相違があると思います。現在の日本は計算できる利便とコストを比較し、利便性が勝れば建設する思想です。短期視点と言えましょう。これに対し欧米は、短期的な損得だけではなく、数字に表しにくい必要性を重視しているようです。長期視点に立って、国防や災害など国民の安全保障を重んずる思想といえます。その結果、ネットワークは人口過疎な地域にまで及び、しかも片側三車線が広く行き渡っています。
また、平成22年10月には中国国際交流協会の招待で北京を訪問し、先方の案内で高速道路を走りましたが、六本の堂々たる首都圏環状道路が運営されています。最近ではオリンピックの開催が拍車をかけたかも知れませんが、インフラ整備に対する国家の強い意志を観る思いがしました。欧米に共通する思想が背景にあるものと推測されます。
欧州共同体(EC)による統合への努力は、かつての「パクス・ロマーナ」(ローマによる平和)を彷彿とさせます。堂々たる石造りの街道(現代の高速道路)ネットワークが、パクス・ロマーナを政治・軍事・経済・社会のあらゆる面で支えたことは、塩野七生「ローマ人の物語 すべての道はローマに通ず」によく描写されています。
短期視点だけで事を進めると、一時期のアメリカのように財政悪化により修理費をカットした結果、道路が穴だらけになったという例もあります。財政事情を見ながらも、長期視点で計画的に事業を進める必要があると思います。
以上
連載第31回「急がれる老朽化対策」
経年変化や塩害による老朽化は、年々加速しています。
NEXCO中日本管内では、開通後30年を経た道路が60%を超えています。なかでも高速道路のシンボルである東名は全線開通後41年、名神は45年が経ちました。新東名・名神の早期完成が待たれる理由の一つは、現東名・名神を交通止めして抜本的な修理をし、道路を長持ちさせるためです。これは現場を見続けている者に共通の思いです。
平成20年5月にある事件が発生しました。高速道路の橋桁から一般道路に、小さなコンクリート破片が落下したのです。親切な地元の方の通報で分かり、直ちに保全・サービスセンターの者が現場に急行して状況を調べ、その日のうちに本社に報告がなされました。
その報告を聴いて、最重要な予兆だと私は受け止めました。これから次々に発生する恐れがある、人身事故が起きてからでは遅い、早急に総力を挙げて対策する必要がある、そうでなければ「安全・安心・快適」を標榜する会社の存在価値がない、と考えました。NEXCO中日本ではその頃から、朝会と称する会合を毎週水曜日に始業前の8時半から開いていました。会長、社長はじめ本部長クラスの幹部七名が集まり、物事が柔らかい段階で経営全般について情報交換をし、自由討論をする場です。ここで全員の賛成を得て即日実行したのが次の方針です。
第一は社長を本部長とする緊急対策本部を設置する、第二は高速道路と一般道路の交差する箇所を全部点検し手を打つ、第三は経費削減中だが人手と費用は一切惜しまない、第四は4月に始まったばかりの平成20年度予算を緊急点検最優先に組み替える、第五はグループをあげて全速で対処する、の五つでした。大雨や地震などによる自然災害のときと同じように、社会的責任の徹底を決めたのです。
その後もコンクリート破片や鉄片の剥落が続きましたが、平成21年春までの一年間でチェックを完了し必要な手当が済むまで、人身や物損事故が起こらなかったのは、本当に幸運に恵まれたと感謝しています。グループの総合力も十分に発揮できたと思います。その上、この一年間の目の色を変えた取り組みが、次の「百年道路計画」に繋がることになりました。
以上
連載第32回「百年道路計画」
百年道路という言葉は、コンクリートの剥落をきっかけに高速道路の総点検を始めた頃、役員との雑談の中で生まれました。
保全担当常務が「百年は保たせたい」と言いだしたのがきっかけで、「そうだ、それはいい。百年道路計画をやろうじゃないか」と決めた経緯があります。地味な維持管理業務に、夢のある目標が生まれたと思います。さかのぼれば塩野七生氏が書いているとおり、古代ローマ時代の街道ネットワーク造りの中にも、同じように明確な保全思想があったのです。
百年道路計画とは、単に「百年もつ道路」ではなく、「百年経っても元気な道路」にする計画です。平成21年4月にスタートした新五カ年計画の中で、経営施策の基本となる柱の一つに据えました。
高速道路は国民の貴重な財産です。それを健康な状態で維持管理し、将来の世代につなぐことは当代の者の責任です。負担を後代に先送りするわけにはいきません。官業よりも民営化会社の方が国民のためになるという判断で、NEXCOが生まれたのですから、いっそう責任は重いと言えます。
道路問題が俎上に上るときは、たいてい建設の可否か料金が話題となります。今ある道路をいかに大事に長持ちさせるかについても、もっと論議されて良いのではないでしょうか。維持管理は、24時間365日切れ目のない地味な仕事ですが、縁の下の力持ちで、新しい道路の建設と同じか、それ以上に重要だと私は思います。高度の技術力と経験を要する、文字通り現場力発揮の場であり、特に災害など緊急時の機動力は、道路運営にとって欠かせません。また、地方の活性化のためにも、小回りのきいた短期の修理改築工事は、かなりの即効性があるはずです。
百年道路計画の最初の取り組みは、現状のやり方で修理を続けた場合と、計画的に早め早めに手を打った場合の、ライフサイクル・コストの比較検討です。社外の専門家を招き研究した結果、2050年までに30%のコスト削減になることが判明しました。そこで、考え方も臨床的な事後保全から、予防の計画保全に改めました。
人間の寿命は「天寿」ですから健康管理に努めても限度がありますが、高速道路の寿命は「人寿」、人次第と言えます。今の世代が知恵を絞って実行しさえすれば、人寿を伸ばすことは可能です。国家百年の計として、意義ある試みと思います。
以上
連載第33回「ETCと料金所」
ETCは平成9年に始まり、短い期間のうちに急速に普及してきました。
現在では通行車両の8割以上、所によっては9割がETCを利用しています。この4年間だけで、普及率は2割も上がっています。料金サービスの内容やゲートでの混雑解消など使い勝手の良さが、利用者に受け入れられた結果と言えましょう。今後どうなるかは無料化構想次第ですが、料金制度の変更は影響が大きいので、利用者への十分な説明が必要と思います。また、料金収受員には高齢者が多く、最近では女性の従業員も増えています。NEXCO三社だけでも、バックアップ業務を含めれば2万人近い関係者が勤めていますので、雇用への配慮も欠かせません。
料金所がらみで二つの事例を紹介します。一つは、有料制を絶対に認めない確信犯による料金所の強行突破です。強制力を持たない収受員ではらちがあかず、中には払わない理由を書いた文書をばらまく者までいました。数は少なくても、ルール違反を放置しては、普通の大多数のドライバーに対して申し訳がたちませんから、警察とも協議して対策を講ずることにしました。幸いにして管内の名神高速道に駐在する滋賀県警の高速隊長が、広域での捜査を行い、とうとう不払いグループのリーダーを遠く離れた他県の料金所で現行犯逮捕し、問題の解決を図ってくれました。それを機に、確信犯による不払いはなくなったのです。
もう一つの事例は、ETC利用車の料金所での速度制限です。規則では時速20km以下となっていても超過するドライバーがたえず、料金所での追突事故が多発し、安全を確保するためにどうしたらよいか頭を悩めていました。その時に社内外の懸念もものかは、敢然と立ち上がったのが金沢支社です。支社長の陣頭指揮で、平成19年にETCバーの開閉速度を遅くする実験が始まりました。広報を徹底し、一カ所ずつ管内の料金所で試行したところ、幸いにして混乱への心配は杞憂に終わりました。ドライバーの協力のお蔭もあって、事故は激減したのです。この北陸三県での成功を経て、平成20年には当社管内の全料金所に及び、平成21年半ばからは当社だけでなく他の高速道路会社でも採用されています。
安全はドライバーと道路管理者との共同作業であることを痛感します。現場での勇気あるリーダーシップが、課題の解決をもたらした好例と言えます。
以上
連載第34回「休憩施設を憩いの場に」
NEXCO中日本には、サービスエリア(SA)とパーキングエリア(PA)を合わせ、休憩施設が166カ所あります。テナントの従業員が1万人、売上げは年間で1400億円ほどの規模です。
幸いにして、管内は産業が盛んで観光名所も豊富ですから、人流・物流ともに恵まれています。しかし、お客様は本当に喜んでくれているのだろうか。これが民営化してから、一貫して変わらない社内に共通する問題意識でした。
SA・PAの管理会社として、平成17年12月に中日本エクシスが設立されましたが、お客様にとって道路、トイレ、ショッピング、スナックやレストランは、動線の中で不可分のものです。そこで、お客様満足を目標に、道路は道路、店は店というような区分けを廃し、NEXCO中日本のグループの総力をあげてサービス向上に取り組んできました。もちろんエクシス社員は、休憩施設運営の専門家としてSAに常駐し、テナントと協力して日々の改善に励んでいます。
新しいアイデアは、こうした雰囲気の中から生まれてきます。主要なSAの大規模改良が数カ所で始まり、計画通り東名阪道御在所SA、名神多賀SA、東名足柄SAのリニューアルが完了しました。これらに続く第二段階の改良も始まっています。写真は、新装なって9月以降に順次オープンした、三つのSAの本館「EXPASA」の模様です。また新東名の開通に向け、新休憩施設の構想も描き上がりました。いずれも地元と協力して、地域色豊かなSA・PAを誕生させる計画です。
市中のデパートやショッピングセンターが苦戦している中で、集客能力のあるSA・PAに注目が集まっています。地元の協力を得て地域色豊かな出店計画が進んでいます。同時にこれら休憩施設を「プラット・パーク」と名付け、外に駐車場を増設し、地域の皆様にも自由にご利用頂けるようになりました。また、二年前に新設した社内の女性・若手社員プロジェクトからは、レイアウトやインテリア、商品計画などで斬新なアイデアが出始め、大規模改良などで次々に採用されています。
お客様に休憩施設で快適な一時を過ごして頂くには、最低の必要条件があると思います。それはトイレとゴミ箱の徹底的な美化、それに草刈りです。八王子支社を起点に、全社に改革が広がり始めました。表面的な清掃だけでなく、臭いの原因を探求し浄化槽の改善にまで対策が及び、ゴミ収集も計画化し、ディズニーランドで学んだ清掃のエリア・キャストの導入など、現場の自主的な工夫による改革に弾みがつき始めたようです。
以上
連載第35回「自然環境との共生」
NEXCO中日本は、平成20年に「環境方針」を一新し、景観理念も新しく制定しました。
新環境方針の内容は、地球温暖化の抑制、資源の3R(リデュース:抑制、リユース:再使用、リサイクル:再資源化)、地域環境への配慮の三つを柱とするものです。この目標を実現するために、技術開発に特に力を入れることとしました。
道路はエコロードを、サービスエリアはエコショップを目指しており、自然との「共生」が何よりの眼目です。西欧流の対峙や征服ではなく、人間社会も自然の一部だとする東洋流の「共生」思想に、今後の環境問題を解く鍵があると思います。日本が世界をリードできるのは、この共生思想と技術力ではないでしょうか。
高速道路を形作る盛り土のり面や橋梁、トンネルは、田畑や町並みに繋がる生活環境の一部であり、より大きな自然環境の一部です。質実剛健で清潔な、周囲に調和した心休まる道路環境作りが欠かせません。
建設副産物では発生土の活用、伐採した草木の堆肥化や燃料用ペレット化が進み、SAでは廃食油を原料とするバイオディーゼル燃料(BDF)が実用化しています。資源ゴミのリサイクル率も、平成22年度は100%を達成する見込みです。
動植物の保護では、地域性苗木の育成(写真)がその一例で、のり面に生育していた樹木の種を採取し、滋賀県栗東市の緑化技術センターで苗木に育て、植え戻しました。元の樹林が戻っています。また、絶滅機種のタヌキノショクダイ(写真)をはじめ多くの希少生物を保護し、ビオトープや獣道なども設置しました。
平成22年10月には名古屋でCOP10が開かれたましたが、建設中の名古屋二環や緑化技術センターの見学会を催したところ、多くの参加者があり、良い反響があったと聞いております。
自然エネルギーによる発電は、今後ますます進むでしょう。平成23年3月に開通する予定の名古屋二環の南東部では、発電量2000kwという高速道路では日本一の太陽光発電が始まります。また、かつて掘削に苦闘した飛騨トンネルの大量湧水は、平成22年12月から小規模とはいえ水力発電に用いられるようになりました。トンネル照明の一部を担っています。手こずった子が孝行息子に変身、現場が生んだ知恵でした。
以上
連載第36回「海外事業は将来の経営の柱」
平成19年4月に、全社的な海外プロジェクトチームが発足しました。
会社の将来を担う事業として、新東名プロジェクトと並んで始まったものです。先進国では、道路ネットワークが完成すれば、幹線道路の建設は減少し、事業の主力が維持保全になることが避けられません。それが確実性をもって予測される以上、今から準備しておく必要があると考え、途上国の道路事業に参入しようと決意したのです。このことによって、長年蓄積してきた世界レベルの技術力、優れた技術者の有効活用を図ることができると考えました。
二大プロジェクトのうち新東名の建設は、不測の事態が起こらない限り先の見通しが立ちます。一方の海外事業は、長期戦になることを覚悟しました。理由は、これまでの海外との関係は技術指導だけで、収益事業の経験は皆無だったからです。強みは世界水準の高い技術力と潜在的な人材力です。技術指導とはいえ海外経験者は数も多く、やる気が十分にあるので、鍛えれば戦力として使えると思いました。
方向としては、経済成長の期待できるアジアを中心に注力すること、高速道路は長期の国家プロジェクトなので日本政府との関係が良い国を選ぶこと、経験不足を補うため国内外の他社と連携すること、社内の人材を養成すること、などを柱として検討を開始しました。
一国の社会インフラを整備する事業は、その国の国造りそのものです。巨大資金を要する上に、十年、二十年単位の長期計画となりますので、官民が連携して当たることが重要と思います。
平成19年末にはベトナムの道路公社(VEC)と覚書を取り交わし、翌20年末にはハノイに高速道路会社としては初の海外現地事務所を開設し、常駐の所長を派遣し、本格的な参入への準備に入りました。例えばホーチミン近辺のカントー橋で維持管理業務を受注するなど、動きが具体化し始めたところです。写真は平成21年冬にベトナム運輸省ドゥック副大臣一行が来日し、東海北陸道の現場を視察した時に撮ったものです。また、マレーシアのPLUS社とも覚書を調印し、研修生の受け入れを開始し、フィリピン、インド、トルコ、インドネシアなどにも調査団を派遣してきました。各国からの来訪者も増えています。国により事業の進展は様々ですが、経済の発展に伴いインフラ整備の必要性が高まることは、特にアジアでは確かだと思います。
道は遠いにしても、一歩を踏み出さなければ志は実現しません。世界は広い。途上国のインフラ整備のために、また高速道路会社としての可能性を求め、持っている技術力を駆使し目標を実らせたいと思います。
以上
連載第37回「社員の「やる気」が会社を伸ばす」
人材は会社の宝です。
重要な経営資源はヒト、モノ、カネの三つ、と本には書いてありますが、これはヒトを単に労働力としか見ない立場か、実務経験の無い批評家の考えのようです。どれほど潤沢にカネや設備や技術の蓄積があっても、ヒトに「やる気」がなければ、たちまち企業は没落し、「唐様で書く三代目」となることは必定です。
経営実務の世界ではヒトは常に主語であり、ヒトは何かをする主体なのです。モノやカネのように扱うことは出来ません。それだけにヒトの「やる気」が企業の死命を制します。組織の長が切に願う社員の「やる気」は、実に捉え所がないものですが、最大の理由はヒトが感情の動物だからだと思います。諸々の改善や改革の企てが、理屈通りにはいかず挫折する原因がここにあります。
ところで、平成20年春頃から経済の変調が実感できるようになりました。リーマンショックの半年前でしたが、物流の動きに今までとは異なる変化が生じているのが分かったのです。そこで、社をあげて思い切った経費削減に舵を切りかえましたが、能力開発は「やる気」を引き出す源ですから、削減対象から切り離し、むしろ増額しました。人事部長以下がキャラバンと称して現場を熱心に回り、社員の教育訓練に対する強い要望を纏め、カリキュラム編成に反映させたのもこの頃です。
「やる気」を引き出す特効薬は何か。私はついに発見できませんでしたが、トップダウンとボトムアップの融合が大前提と考え、経営理念のとおり、「衆知を集める」ことにしました。効率は落ちますが、辛抱強く、急がば回れです。むろんある程度論議しても答えが出ない場合は、トップが断を下すという前提です。ヒントは明治新政府が掲げた五箇条の御誓文にある、「広く会議を起こし万機公論に決すべし」でした。
組織のトップは最初は先頭を走る、皆の「やる気」が出始めたら集団の中に自然に溶け込む、組織の自律性がもっと高まれば集団の後方で軌道修正をする。これが私の描く理想のリーダー像ですが、実際は一筋縄ではなく、行ったり来たり、試行錯誤の連続でした。
土光さんの言葉で、「社長は偉い人ではない。役割が違うだけだ。上も下もない。上に立つ者は権力を振りかざすな。権威で仕事をせよ」とあります。権威とは長年の経験と思索に基づく、優れた判断力と部下からの信望でしょうか。組織の上下左右、お互いのチャレンジとクイック・レスポンスを求めてやまなかった、土光さんの面目躍如です。
以上
連載第38回「国際NGO活動への参画」
平成22年6月に退任してからは、仕事面では(財)産業雇用安定センターの会長職と、直後の7月に自ら設立した株式会社ADES経営研究所を主とする積りでした。ところが、10月になって急遽NEXCO中日本に顧問として復帰し、東京で勤務することとなりました。
本業以外では、長く携わってきた国際ボランティア活動にも力を入れたい考えです。(社)国際IC日本協会とCRT日本委員会の二つで、私は橋本徹氏(富士銀行元頭取・会長)の後を承け、2年前から会長を務めています。
IC(イニシアティブズ・オブ・チェンジ)は、1938年にMRA(道徳再武装)として英国に始まり、2001年にICと名称変更しました。本部はスイスのレマン湖畔コーにあります。戦後の英仏和解や日本の国際社会復帰に大きく貢献しました。日本では昭和50年に国際MRA日本協会として組織化され、初代会長には土光さんが就任しました。当時の専務理事が藤田幸久氏(現参議院議員)です。昭和51年に東京で第1回国際会議が開催された際、私は事務局の手伝いを命ぜられ、初めて各国の人々と接するようになりました。そして今も親しい交流を続けています。昭和52年から東芝労使の一員として、何度かコーの世界会議に参加したのも良い体験でした。
IC日本は毎年コーの会議に参加するほか、国別にも親密な関係を保ち、とりわけ中国、インドとは定期会合を重ねています。平成22年10月中旬には、中国国際交流協会の招きを受け、私が団長として北京、成都、上海を訪問し、親交を深めました。平成23年には中国チームを日本に招待します。また、10月にはインドのムンバイ近くのパンチガニで、日印ICの共同主催による第3回国際会議「コー・イニシアティブ・フォア・ビジネス(CIB)」を計画しております。
CRT(コー・ラウンドテーブル)はMRAが生みの親です。1987年に日米欧の経営者が経済摩擦の解消のため、コーに集まった円卓会議が始まりです。1994年にはCRT企業行動指針として実り、CSRに関する民間版の世界モデルとなりました。私も何度か会議に参加し、キャノン加来龍三郎氏の「共生」理念が、欧米の経営者に深い敬意をもって迎えられた場面にも立ち会いました。日本が提唱した「共生」に加え、欧州の「人間の尊厳」、アメリカの「ステークホールダー原則」の三つが、行動指針を支える理念となりました。
幸い両団体とも、学生などのボランティア参加が盛んで、親密な国際交流を通じて、次代を築く若者の育成にも貢献したいと考えています。
以上
連載第39回「趣味の世界に遊ぶ」
時間潰しではない本格的な趣味の世界を広げたいのですが、多少ともモノになるのは長年続けている種目に限るようです。私の場合、少年時代に始めた柔道は今や団体のお手伝いで精一杯、囲碁だけは何とか現役を続けています。
その囲碁も10数年まともな対局から離れていたところ、3年前に名古屋の日本棋院中部総本部で、山城宏九段に二子を置いて教えて頂きました。ゆったりと正攻法で、少しも急がず、こちらの悪手で次第に形勢が傾きました。碁はこういう風に打つものかと、心から感服しました。お蔭で長年のブランクを取り戻した感があり、「まだ強くなれますよ」という言葉を真に受けて、励んでみようと思っています。
名古屋での収穫に、陶器があります。休日に窯元を訪ねる楽しみを覚えたのです。美濃の人間国宝加藤孝造氏、伊賀の土楽窯福森雅武氏とお会いし、味わい深いお話を伺い、親交を深め、いろいろと啓発されました。只今はもう少し深く踏み込んで、これからの十年の楽しみにできればと思っています。
音楽の関係では、平成元年に東芝フィルハーモニー管弦楽団(TPO)が社員中心に結成され、広報室長であった私は初代団長(現顧問)を仰せつかりました。結団の中心となった柏木成豪君(第二代団長)らに推されたのです。名誉団長は佐波正一相談役にお願いし、今も変わらぬご指導を頂いております。
その後TPOは平成8年の5月連休を利用して、アメリカ演奏旅行を敢行しました。西海岸から始まり各地で歓迎を受け、最終日はニューヨークのカーネギーホールで、「切符売り切れ(Sold Out)」の盛況となったのです。佐波名誉団長は公演終了後のパーティーで、団を代表して多くの来客を前にお礼の挨拶をされました。その中で9年前のCOCOM事件に触れて、次のように述べました。
「当時のアメリカに比べ、今回の各地での暖かい歓迎ぶりは様変わりで、言葉に尽くしがたい」と。道義的責任を取って東芝の会長を辞任された当時を知る者にとっては、万感胸に迫るものがありました。
各地のマスコミも関心を持ち、経済でもスポーツでもない、日本の文化使節として好意的に迎えてくれました。カーネギーホール公演の朝、私は急遽CNNのテレビスタジオに招かれ、生放送のインタビューを受けたほどです。自主運営の企業オーケストラがよほど珍しかったのでしょう。コンサートマスターの佐藤秀夫君やチェロの柏木君ら、団のトップ奏者が弾く弦楽四重奏を背景に応答し、舞台での席次は年功ではなく実力順だと話したら、ひどく感心してくれたのが愉快でした。
以上
連載第40回「お爺ちゃんの論語塾と家族」
長いあいだ暖めてきた思いが、やっと日の目を見ました。「お爺ちゃんの論語塾」なるものを、平成22年7月上旬に自宅で開いたのです。
『論語』は私の座右の書です。長年親しみ、繰り返し読み続け、参考書も数多く繙きました。訓詁の学や堅苦しい儒学には興味がなく、『論語』そのものに直接向かい合ってきました。中学生の頃に初めて接してから、40歳になってやっと全巻を読み通し、歳と共に味わいが深くなり、読むたびに新しい発見があります。孔子は私にとっては、酸いも甘いもかみ分けたお爺ちゃんのような存在で、何か困った問題に直面すると、早速ページを開いて相談するという具合です。
会社の幹部研修ではいつも『論語』を引用しましたが、何とか孫の世代にこの素晴らしさを伝えることは出来ないかと考え、早速開塾することにしたのです。毎週一回、一、二章ずつ読んでいます。素読が基本で、簡単な解説をしますが、必ず暗記するように指導しています。入塾した弟子は、現在のところ四人です。本命の孫が小二と小五の男の子で二人、それに何と私の妻と、末娘の伴侶も加わりました。彼は英国で大学まで教育を受けた青年で、東洋のことを勉強したいと入門してきたのです。
少年たちにとっては、漢字は少しも難しいものではないようで、面白がってたちまちのうちに記憶してしまいます。意味は大きくなれば分かるようになる、お爺ちゃんもそうだった、と話しております。
実は思うところあって同じ7月下旬に、(株)ADES経営研究所という経営コンサルタントの会社を設立し、代表取締役社長に就任しました。港区南青山に事務所を設け、電話番がいるだけで中味はこれからですが、「お爺ちゃんの論語塾」は、この会社の社会貢献事業の一つにしようと考えています。
妻の景子とは結婚して46年、いつも良き戦友で、協力者で、柔らかな批評家でもあります。二人で始めた生活がいつの間にか14人の大所帯になりました。四人の子供達、泰弘・直子・義典・智子はそれぞれ良き伴侶を得、独立して好きな道を歩んでいます。写真は、私の会長退任を記念して8月初めに、長男の音頭で全員集合し、慰労会を催してくれた時のものです。楽しい一時でした。
私たちも平生は夫婦二人きりの生活になりました。それぞれに色々とやりたいことがありますし、できれば少しでも人様のお役に立てるよう、揃って元気に過ごしたいと考えています。
以上
連載第41回「天命を信じて人事を尽くす」
古来の名言に、「人事を尽くして天命を待つ」という言葉があります。
やれるだけのことはやって、あとは天命にゆだねる、結果はどうなろうとも悔いなし、ということです。宮本武蔵が最晩年に「独行道」をしたため、その中に「我事におゐて後悔をせず」と記した心境も、同じであったかも知れません。まことに爽やかな態度であり、男らしくて申し分ない、と私は長年思ってきました。少なくとも40歳になる頃までは。
しかし、不惑の歳を迎えた30年ほど前から、少し違うのではないか、これでは安心立命はできそうにないと考えるようになりました。仕事の結果が気になって仕方がなかったからです。人事を尽くしてないからだ、と反論されれば引き下がるほかありませんが、心は納得しなくなったのです。会社の管理職に成り立ての頃で、良い結果を求めて焦っていたのかも知れません。堂々巡りに陥っていたのです。
私の不惑は迷ってばかりの40歳でしたが、惑わなくなるには今の自分に根本的に足りない、何か確固としたものが必要だと考え始めました。そこで拠り所として選んだのが、長年親しんできた東洋の古典です。とりわけ、『論語』の世界に入り込み、単なる教養としてではなく、生きる指針を得たいと懸命に求めました。
そのようにしてバタバタあがいている内に、ある日ふと思いついたのです。「人事を尽くして天命を待つ」のではなく、「天命を信じて人事を尽くす」ことができれば、どれほど安心して、迷いなく日々を生きていけるのではないだろうか、と。ではどうすれば天命を知ることができるのだろうか。これが次の命題となりました。
天命はいくら本を読んでも分かりはしない、誰も教えてくれることはない、自分で見つけるほかはありません。仕事や家庭など自分の生きている場にまっすぐ対面して、静かに「心の声」を聞くほかに知る方法はない、つまるところ日々の生活の中に答えがある、と思い極めました。
自分は天命によって生かされているのだ、と信ずることが深ければ、迷いの中にも「心の声」が聞こえてくるように思われます。全て自己流で何の作法もありませんが、毎朝未明に起き、できれば野の花とともにひとり坐って、「静かな瞑想の時間」を持つ、そこから聞こえてくる声には気の重いことでも素直に従う。そうした毎日をこれからも過ごしたいと思います。今の私には、『論語』のほかに、『易経』『老子』『正法眼蔵』などが座右にあって、怠惰を戒めてくれます。
以上
連載第42回「スイスは何故安定しているのか」
昭和52年の夏、東芝労使は揃ってスイスの会議に参加しました。
前年の第一回MRA(道徳再武装)東京国際会議に出席して、労使共に得るところがあり、あらためてレマン湖畔のコーで開かれるMRA世界産業人会議に参加することにしたのです。高瀬正二常務と河野一義副委員長(翌年委員長)はじめ、東芝グループの労使半々で10人のチームを編成し、労働課長であった私は団のお世話係を務めました。
いよいよ明日出発という時、高瀬さんに連れられて土光さんに挨拶に行きました。すでに経団連会長でしたが、東芝会長として毎日のように本社に見えていたのです。高瀬さんが型どおり出張の挨拶をすると、土光さんは打てば響くように答えました。「それは大変良いことだ。しっかりやってほしい。ついては、調べてきて貰いたいことがある。石油危機語の経済破綻で各国が苦しんでいる中、スイスの経済・社会が安定しているのは何故か、確かめてほしいのだ」というご下問です。
部屋を出るなり、当然ながら高瀬さんから「おい、頼むぞ」と言われました。時間がないため作戦は単純明快、現地でなるべく多くの人から直接話を聴くことにしました。高瀬さんと一緒にスイス人の事業家、国連機関の幹部、社会活動家、駐ジュネーブ日本大使など10人ほどに会うことができ、聞き書きを元に粗末な手書きの報告書を作り、帰国後土光さんに提出したのです。高瀬さんの後日談では、「土光さんはあのコピーを持ち歩いて、全国各地で話しているようだぞ」とのことでした。
内容はいたって簡単で、「国民の質素な日常生活、他国と競合しない産業の育成、国民皆兵による国を守る意識」などを、事例とともに三頁に纏めたのです。なによりも私が感服した点は、出張の挨拶に現れた部下に対して、直ちに大きな宿題を与えたことです。普段からいかに深くものごとを考え続けているかの証拠です。この問題意識の深さに、畏敬の念を覚えました。
労使で参加したコーの会議自体も収穫がありました。東芝としては故石坂泰三氏が昭和25年に訪れて以来のコーですが、世界中の人々から温かい歓迎を受けました。団を代表して高瀬さんが演説した「日本の労使関係」も、高い関心を呼び起こしました。内容は河野さんはじめ労組団員の意見も十分反映したもので、「労使対等・相互信頼・事前協議」の三つを日本的労使関係の特徴としてあげました。東芝労使はこの時から続けて代表団をコーに送るようになったのです。
以上
連載第43回「裏街道を歩いた土光さん」
おかしな題を掲げて恐縮です。何の意味かと首をかしげられても仕方ありませんが、これは土光さんが工場の現場を視察している光景を実見して、駆け出し社員だった私が感じ取ったありのままの印象なのです。
昭和40年、土光さんは東芝の社長に就任しました。直ちに工場など現場視察を始めた最初の頃、川崎市のトランジスタ工場(現多摩川工場)を訪れました。私は新人として配属されて三年目の夏、総務部の一員として興味津々でお迎えの準備に加わりました。
前社長は工場を視察することが殆どなかったようで、どのような迎え方をしたらよいか勝手が分かりません。とにかく視察経路を決め、要所要所に課長クラスの説明員を配置し、工場長以下部長数名がお供して巡回しようということになりました。何をさておいても隅々まで綺麗にしようということになり、不要なものは片付け、床、壁、トイレなどの清掃に努めました。
その当日になって、土光さんは何と言われたか。「案内は工場長一人でよい。質問には工場長が答えてくれればよい」ということになりました。お供の部長も現場の説明員も、仕事をやっていなさいという意味だったのか、工場長に対するテストだったのか、あるいは大袈裟を嫌う土光流だったのか、理由は想像の域を出ません。
お茶を一杯飲んだだけで、直ちに四階建て二棟の現場に入り、本当に熱心に、丁寧に、製造工程を視察されました。その途中で土光さんの指摘を受け、予定になかった出来事が二つ発生しました。
一つは、エレベーターホールの隅にある鉄のドアを、「中に何があるのか」と開けさせられたことです。実はそこには職場を綺麗にするため不要不急となった機械、机や椅子などの備品を一時凌ぎに詰め込んであったのです。一同大いに赤面したことは言うまでもありません。二つは、「倉庫を見せなさい」でした。製品と部品の倉庫に入り、ラベルや保管状況まで見て回る徹底ぶりでした。在庫の回転率、不動在庫や死蔵の有無、棚卸しの状況、ゴミや埃の具合まで、つぶさにチェックされたのだと思います。
一見して裏街道が、実は一番大事な表通りだったのです。
その日から工場を挙げて、徹底的な美化が始まりました。短期間の内に、いつ誰が見に来ても大丈夫という域にまで達したと思います。世間で生産性向上のために、5S運動(整理・整頓・清掃・清潔・躾)が叫ばれるようになる遙か前のことでした。工場の本格的な意識改革の始まりです。
以上
連載第44回「大型人材はどうすれば育つか」
昭和50年前後のことです。東芝では大型人材の育成を図ろうとする、意欲的な企てが始まりました。人事部と人材開発部が中心になって、企業における大型人材とはいかなるもので、それを育てるにはどうすればよいか、真剣に喧々諤々の議論が行われたのです。
大型人材と目される人物を分析しその特徴を抽出し、国際化(当時はグローバル化という言葉はまだそれほど普及してなかったと思います)や不確定性など今日的課題が求める必要性をまとめ、箇条書きで人物像を描き出しました。理想の大型人材像が出来上がったのです。先見性、コミュニケーション能力、指導力、国際性、協調性、健康、語学力などなど、いろいろな属性や資格要件が列挙されました。それを実らせるための方法としては、徹底的な教育訓練を施すこと、具体的には、実務を通じた訓練OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)を主とし、それを補うものとして座学OffJT(オフ・ザ・ジョブ・トレーニング)のメニューが整えられました。目標管理を強化し、仕事の与え方や、動機づけの手法も開発され、従業員の満足度調査なども行われたのです。当時の行動科学の研究成果も十分反映されていたはずです。
さて、最終案を携えて土光さんに説明した時のことです。この場面には私は同席しておりませんので、後日人づてに聞いた話ですが、土光さんは、「結構なことだからやりなさい。ただ、大型人材は大型人材の下でしか育たないものだよ」と言われたそうです。本物だけが本物を育てることができるという、教育する側の重要性を指摘されたのでした。おそらく長年の体験に裏付けされた、実に含蓄の深い、人間教育の本質をついた批評だと思います。説明者はおそらく冷や汗をかいたのではないでしょうか。
「上に立つ者は、まず自分自身を鍛えよ。自らの人格識見を高めよ。目標を掲げ、困難には率先してぶつかれ。部下はついてくる」と獅子吼したのだと思います。行動の人であった土光さんには、語り継がれてきた逸話が多くありますが、ひとつ紹介します。
かつて地方の電力会社に納めた大型機器に大きな不具合が生じた時、土光さんは部下に任せることなく、海外出張から帰国したばかりの空港から家にも会社にも戻らず、ただちに相手方社長のもとに駆け付け、謝り、事後処理に万全を期したと聞いています。品質などの大問題を起こした時に、それを契機に相手との信頼関係を深め得るのは、誠心誠意しかありません。土光さんはそれを率先して実行され、後に続く者の良い模範となったのです。
以上
連載第45回「拳にタオルを巻いた怒号さん」
こわい土光さんを見たことがあります。
東芝の社長として最後の頃でした。私がある日秘書室に用事があって出向いた時に、たまたま役員フロアの廊下で土光さんとすれ違いました。役員会議室から勢いよく現れた土光さんは、手洗いに向かう様子でしたが、何と右手の拳(こぶし)にタオルを巻きつけていたのです。
ころんで怪我でもしたのかと秘書に聞いたところ、そうではなく、役員会議でテーブルを叩いて議論しているうちに、拳の皮膚が破れて血が出たので、包帯代わりにタオルを使ったのだそうです。驚くやらあきれるやらで、絶句してしまいました。
何を論議して、どうしてそうなったのかは、蚊帳の外の者に分かりませんが、その恐るべき迫力に鳥肌が立ちました。仕事とはこれほどの気合いでやるのかと思いました。土光さんが、別名「怒号さん」と呼ばれているのは知っていましたが、現場に立ち会ったことはありませんし、私たちのような若い者には常に温顔で接していましたから、正直のところ実感がわきませんでした。
ただし、一回だけ片鱗に触れたことがあります。土光さんが「役員は皆首だ!」と、怒鳴っている現場に居合わせたのです。
昭和51年春だったと思います。東芝の定例中央労使協議会が開かれ、続く労使の懇親会が終わった時のことです。定例中央労使協議会は春秋の年2回、会社側は社長以下が出席して行われるものです。この日は夕刻の懇親会に、会長だった土光さんが飛び入りで参加しました。電々ビルの地下2階、社員食堂を利用した簡素な立食パーティです。土光さんが久しぶりに顔を出したこともあって、労働組合の幹部も大喜び、懇親会はたいへん盛り上がりました。そのうち一人帰り二人帰り、最後の組合幹部が去った時に会場に残ったのは、土光さん、労働担当役員の高瀬正二専務とその部下だけでした。私は労働課長でしたから当然そこに居合わせました。そこでこの爆弾発言が飛び出したのです。
「懇親会では組合がお客さんだ。お客さんが一人でも残っている時に、ホストたる役員たちがさっさと居なくなるとは何事か。そんな役員は皆首だ!」となったのです。他の役員は労担役員に後を任せたつもりだったのでしょう。それが世間の常識なのかもしれませんが、土光さんは決して許すことはなかったのです。お客様に接する姿勢とはこうでなければならないのかと、目から鱗が落ちる思いがし、この気持ちを忘れないようにしようと私は心に深く誓いました。
以上
連載第46回「日々に新たに」
土光さんは揮毫を求められると、しばしば「日新、日日新」という句を墨書しました。
四書のひとつ『大学』に、「湯の盤の銘に曰く、苟(まこと)に日に新たに、日々に新たに、又日に新たなり」と記されている言葉です。あまりに有名すぎて、浅学の者が解説するのはおこがましいのですが、夏の暴君桀王を倒し、殷王朝を開いた湯王が、水盤の底に記して、毎朝顔を洗うたびに心を励ましたと伝えられています。紀元前1600年、今から3600年前のことです。
『大学』は『論語』と並ぶ四書の一つ、江戸時代の青少年教育の基本となった書物で、武士の子弟だけではなく、私塾や町の寺子屋でも教えられました。二宮金次郎が薪を背負って読んでいる本が『大学』だそうです。武士だけではなく志ある人々には、それこそ骨の髄までしみ込んでいたことでしょう。将来ある若者の心構えとして、少なくとも終戦までは、絶えることなく語り続けられてきました。しかし、これを日常生活の中で、生涯をかけ、たゆまず実行し続けた人は、昔からそう多くはないはずです。土光さんはその稀な一人であったと私は思います。
幕末の大学者で「言志四録」四巻を著わし、西郷隆盛はじめ維新の指導者たちに絶大な影響を与えた佐藤一斎は、「言志晩録」の中で次のように述べています。「少にして学べば、則ち壮にして為すあり。壮にして学べば、則ち老いて衰えず。老にして学べば、則ち死して朽ちず」と。秀才と讃えられて難関大学を卒業した青年が、四十、五十にして名も聞こえず、壮年時代に名声を博したやり手が、歳をとって昔の自慢話しか能がなくなり、人から煙たがられて行く。悲しいかな人にままあることです。
それに比べて、土光さんの人生は終生いかに若々しかったことか。自慢話など気配さえありませんでした。「自分は過去を振り返るのは苦手だ」と述懐さらくらいです。質素なお宅の応接間兼書斎は、本の重みで根太が緩むほどであったと聞きます。早朝と就寝前に読経をして心を整え、暇さえあれば読書し、畑を耕し、深く思索する日々であったのだろうと想像します。
人知の及ばざる世界を知るがゆえに法華信仰の世界を持ち、自ら至らなさを知るがゆえに孜々として努めてやまない、そういう人生だったのではないかでしょうか。ご母堂の遺志を継いで橘学園という女学校を経営し、収入のほとんどをそこに注ぎ込み、自らは奥様ともども極端に質素な生活に満足したというような、形は誰にも真似のできることではありません。しかし、その志したものを求めることは、凡人にもできることだと私は思います。
以上
連載第47回「一以てこれを貫く」
長年親しんできた『論語』には、好きな言葉がたくさんあります。ここに掲げた「一以貫之」もその一つです。原文を再現しますと、次のように記されています。
子曰く、参や、吾が道は一以てこれを貫く。曾子曰く、唯(い)。子出ず。門人問うて曰く、何の謂いぞや。曾子曰く、夫子の道は忠恕のみ。(里仁編)
孔子が弟子の曾子に言った、「参(しん、曾子の名)よ。わが道は一つのことで貫かれている」。曾子は答えた、「はい」。門人が曾子にたずねた、「どういう意味ですか」。曾子は答えた、「師の道は、忠恕(ちゅうじょ)のみです」と。
禅問答のような師弟のやり取りを聞いて、ついて行けなかった他の弟子たちが、孔子が部屋を退出した後で、曾子に意味を問うたところ、答えは「忠恕のみ」ということでありました。金谷治訳注「論語」(岩波文庫)によりますと、忠は内なるまごころにそむかぬこと、恕はまごころによる他人への思いやり、とあります。曾子は孔子よりも46歳も若いながら、師の心をよく理解していた出色の弟子でした。後に『孝経』『曾子』を著し、孔子の教えを後世に伝えた逸材です。
「恕=おもいやり」は、孔子が『論語』全巻を通して最も大切にした価値観であり、別のところにその意味をもっと掘り下げた問答があります。
子貢問うて曰く、一言にして以て終身これを行うべきものありや。子曰く、それ恕か、己の欲せざるところ、人に施すことなかれ。(衛霊公編)
弟子の子貢が質問した、「一言で一生行うべきことを挙げれば何でしょうか」。孔子が答えた、「それは恕だ。自分の望まないことを人にしてはいけない」と。
子貢は孔子塾の中で子路と並ぶ先輩格として重きをなし、理財に長じ、優れた事業家として富を築き、孔子塾の経済を支えました。先生の孔子をはじめどう見ても儲けることは下手な集団ですから、子貢の存在は貴重だったと思います。言語の人と称されるほど弁論が立ち、孔子との問答にもしばしば登場し、私たちが尋ねてほしいと思う問いを、次々に発してくれます。弁が立ちすぎて、時々孔子にたしなめられてはいますが、世俗にあって道を求めた経済人として、親しみを覚える存在です。
「一以貫之」の出典は以上ですが、必ずしも「恕」と結びつける必要はなく、幅広く色々な使い方があって良いと私は思います。終始一貫して何事かを実行しようとする時など、自由に活用してみてはどうでしょうか。冴えた語調なので、気持ちが盛り上がり、強い決意を伝えることができます。
以上
連載第48回「人物の条件」
どういう人物が組織のリーダーとしてふさわしいか。古くて新しい課題です。いつの時代でも人選びは常に悩みの種でありました。国でも団体でも、組織の盛衰はリーダーの資質次第で決まり、ひとたび人選を誤れば、行く末は目に見えているからです。『論語』は全巻にわたって、この切実な問いに答えています。
ここで取り上げるのは、子貢が孔子に「士(指導者)とは何か」と問うた一節です。畳みかける弟子の問いに、師匠は丁寧にしかも断乎として答えます。人物論において白眉の問答です。
子貢問うて曰く、如何なるをこれ士と謂うべきか。子曰く、己を行いて恥あり、四方に使いして君命を辱めず。士と言うべし。曰く、あえてその次を問う。曰く、宗族孝を称し、郷党弟を称す。曰く、あえてその次を問う。曰く、言必信行必果、コウコウ然たる小人たるかな、そもそも以て次となすべし。(子路編)
孔子は人物を三つのランクに分けました。第一級は「自分の行動に恥を知り、国命を帯びて使いして他国に辱められない人」、第二級は「親孝行で、目上によく仕える人」、第三級は、「発言に信義があり、行えば結果を出す人」としています。今の私たちは子貢のお陰で、第三級までのランキングを知ることができました。
注目したいのは、「恥を知ること」が人物の条件の第一にある点です。無恥で強欲な人間は何をしでかすか分からないという懸念は、昔も今も変わりなかったのでしょうか。まさに至らざるところなしで、最近の不祥事も大半の原因はここにあります。ただし、当人が恥を知る人であるかどうかは、一見して外目には分かりません。その点について人間通の孔子は、行動や、動機や、喜ぶところを見ていれば、人間性は隠しようがないと述べています。人の評価には時間をかけて観察せよ、と教えているのです。
その以(な)す所を視、その因る所を観、その安んずる所を察すれば、人いずくんぞかくさんや。人いずくんぞかくさんや。(為政編の10)
もう一つ。現代流では聡明才弁タイプの「言必信行必果」型の人物が第一級にランクされても良さそうですが、そうしなかったのは何故でしょうか。私の解釈では、単に軽いというのだけではなく、真の指導者には言行に信義と結果が付属するのは当然で、優れてはいるが第一級と評価するほどではない、大勢の人を率いるには、事を処する能力よりも人格的な面が何よりも重要である、としたのだと思います。
以上
連載第49回「孔子と酒」
『論語』に心から親しみを覚えたのは、孔子の日常生活がつぶさに記された郷党編を読んだ時です。
この日から、私にとって孔子は堅苦しい道徳が凝り固まったような聖人君子ではなく、酸いも甘いも噛み分けたお爺ちゃんのような存在になりました。あまりに神聖視しすぎることによって、血の通った暖かみのある孔子を見失ってはならないと思います。私自身が開いた私塾に「お爺ちゃんの論語塾」と名付けたのも、こうした人間臭さに名前だけでもあやかろうとしたからです。
親しみを込めて読み返すうちに、また年とともに、郷党編だけではなく他の編にも数多く、孔子の真情、喜怒哀楽が溢れていることを知りました。天の理を語りつつ、弟子を褒め、叱り、泣き悲しむ孔子がそこにいます。『論語』という形で孔子の言行録をまとめた弟子たちの、師を慕うまなざしが隅々にまで感じられるのです。
例えば、「酒の飲み方」についての下りです。
ただ酒は量なし、乱に及ばず。(郷党編)
酒困を為さず。(子罕編)
「唯酒無量、不及乱」は、孔子の食事の仕方などを記した郷党編の一節の中にあります。間違っているかもしれませんが私は、「酒はいくら飲んでも、乱れることはなかった」という意味に解しました。直感では、巨漢の孔子は相当な酒豪であったに相違ないからです。きっと孔子は背筋を伸ばして泰然自若、柔らかな雰囲気で、斗酒なお辞せず、悠々と酒を楽しんだのではないかと想像します。酒で失敗する人は昔からいくらでもいたのでしょうか、子罕編では孔子自身が自らのこととして、「不為酒困」、酒で人を困らせることはなかった、と語っています。
最近はあまり酔っぱらいを見かけなくなりました。かつては肩を組んで街中を高歌放吟するなどの光景は、少しも珍しくありませんでした。今でも酒癖の悪い人は居ますが、概してずいぶん行儀が良くなったと思います。日本人が酒に強くなったのではなく、そもそも酒を飲まなくなり、まして馬鹿馬鹿しい飲み方をしなくなったのでしょう。田の楽しみが増えたのかもしれません。私たちの世代は多少でも飲める口の場合は、若い頃に例外なく上司や先輩から説教されたものです。「酒は飲んでも飲まれるな」と。
この教訓は口継ぎで伝えられた世俗の知恵の一つですが、一体いつ頃から言われるようになったのでしょうか。江戸か明治か戦後かという疑問を抱いていました。『論語』の「唯酒無量、不及乱」に遭遇し、もしや2500年前の孔子以来のことではないか、と勝手に得心したことでした。
以上
連載第50回「詩と音楽」
門弟3000人と言われた孔子塾では、何を教えていたのでしょうか。興味あるところですが、少なくとも詩と礼と樂の三つは、必修科目であったと思われます。次の一節があります。
詩に興り、礼に立ち、樂に成る。(泰伯編)
人間の成長は、「詩によって言葉の力を学び情操を育て、礼という社会のルールを身につけることによって一人立ちし、音楽によって人間的な完成に至る」としています。孔子は古くから伝わる詩305編を選び、五経の一つ『詩経』として纏め、弟子たちに教えました。弟子の子貢が「切磋琢磨」の語源となった詩について感想を述べ、孔子に「ともに詩を語ることができるね」と褒められた場面が学而編にあります。子貢の喜びが目に浮かびます。
「礼」には、単なる礼儀作法や儀式にとどまらず、社会のルールという広い意味があると思います。当時の儀式は政治そのものでしたが、とかく形式化する中で、どうすれば生きた伝統にすることができるか、に孔子は腐心したようです。
「音楽」に対する孔子の傾倒ぶりは相当なものです。鋭い耳と豊かな感受性を持ち、終生自らも楽器を演奏して楽しみました。こんな一節があります。
子、斉にありて韶を聞く、三月肉の味を知らず。曰く、図らざりき、楽を為すのここに至らんとは。(述而編)
魯の孔子が若い頃、隣の大国斉に留学しました。そこで聞いた音楽が、古代の舜時代の管弦楽である韶という曲です。あまりの素晴らしさに感激し、三か月はご馳走の肉の味も分からなくなってしまいました。孔子は、「想像もつかないことだった。音楽をやることがこれほど素晴らしいことであったとは」と述懐したのです。
注目したいのは、「不図、為樂之至於斯也」です。ここで孔子は、「音楽を聞く」こともさりながら、「音楽を為す」ことの素晴らしさに目覚めたのだと確信します。名人の演奏を聞いて、自分もやってみようと決心し、それを実行してみた。三ヶ月間は名演奏に感激のあまりボーっとして味覚を失ったのではなく、自分も楽器に本格的に取り組み、名人について習い、時の経つのを忘れ、食事は二の次にして没入したに相違ありません。自己流の解釈ながらこのことに気づいて以来、『論語』全体が一段と精彩を放ちだした気がします。
2400年前といわれる曾候乙墓(そうこういつぼ)の発掘によって、往時の楽器を今にしのぶことができます。殺伐とした戦国時代にあって、諸国歴訪の苦境の中でも、国もとの塾でも、常に師弟の間には音楽が鳴り響いていたのではないでしょうか。
以上
あとがき
新書版にあたり、第一部に加筆するとともに、新たに第二部を起こして、土光敏夫氏と『論語』のことを書き加えました。
土光さんについては、数多くの伝記や言行録が出版されています。付け加えることはないのですが、私自身がじかに接して得た小さな体験をいくつか綴ってみました。心に残ることばかりで、後の人生の支えになっています。
本の題とした「青草も燃える」は土光さんの言葉で、若い頃に私が子会社の再建に携わった時、はなむけに頂いたものです。座右の銘にしております。
『論語』は実に不思議な本です。読み返すたびに新しい発見があるからです。最初は有名な学者の解説書から入ったのですが、次第に自分の人生につき合わせて読み、考えるようになり、定説に心が響かない場合は、自分勝手な解釈が始まります。そして遅々としてですが、マイ・ブックになってきました。
古くから、「読書百遍、意自ずから通ず」と申します。私は40歳になった時に、『論語』でこれを実行しようと決めました。百回読んでも通ぜず、さらに百回読んでも結果は同じでしたので、それ以来記録をつけるのをやめています。この箴言は、「良書は読めば読むほど、深い意義が開かれる」と、今は解釈しています。
本書の出版にあたっては、多くの方々のお世話になりました。「マイウェイ」連載中に読後感を寄せて下さった先輩知友の皆様、新書版を企画された中部経済新聞社の恒成秀洋営業局次長兼事業部長、マイウェイ担当の竹尾文博記者、写真などを拝借した土光哲夫氏(敏夫氏次男)、日本経団連、東芝広報室、NEXCO中日本広報室の皆様、そのほか懇篤なアドバイスを頂いた多くの方々に、心からお礼を申し上げます。有難うございました。
これからは少し時間に余裕ができましたので、公私ともにもう少し世の中のお役にたち、ご恩返ししたいと思っています。
平成23年2月 矢野弘典
以上
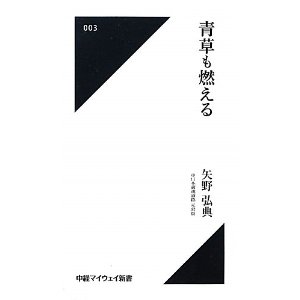
 Services
Services
